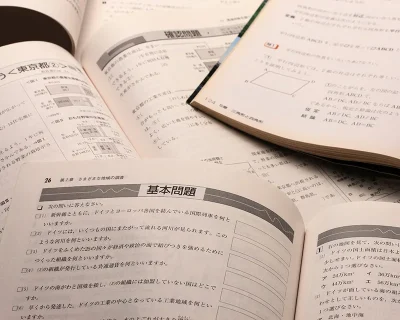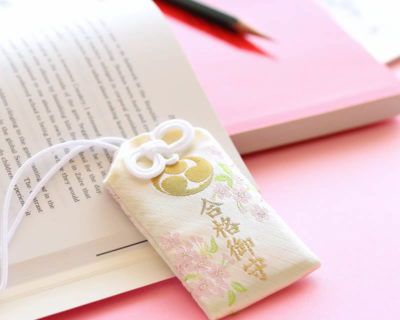受験勉強の体力作りはどうする?付け方 運動は勉強にプラス

受験勉強には体力が欠かせないと言われています。
なぜなら、受験勉強では1日に7時間から8時間以上も勉強することがあり、集中力を維持するためには「勉強体力」と呼ばれる持続的な勉強を支える体力が必要だからです。
これは一般的に言われる「運動の体力」ではなく、「勉強を1日に何時間も続けられる体力」を指しています。
この「勉強体力」は、長時間の勉強が求められる受験勉強において重要ですので、後半で「勉強体力」を向上させる方法を紹介します。また、実は「運動の体力」が「学力」とも関連していることが調査で明らかになりましたので、その点についてもお伝えします。
いくつかの研究によると、「運動能力」が高い人は「学力」も高い傾向があることがわかりました。今回は、ある調査を基に、体力があることで成績が向上するデータや、運動によって記憶力が向上したという結果、受験勉強に必要な体力の養い方についてお話しします。また、基礎体力の向上方法や、受験後の体力回復についても触れていきます。
こちらの記事もオススメ。部活動は◯◯にやるのが成績に一番良い!?
こちらの記事もオススメ。東大生が勉強時に食べるお菓子とは!?
- 目次
運動ができる子は勉強もできる傾向にある!運動と学力の相関関係

まず体力がある方が成績も良い傾向にあるという多治見市教育委員会の調査結果を紹介します。
こちらは多治見市を含む3市による調査で小学生1352人、中学生1065人を対象に行われました。
体力合計点をA~Eに分けたグループに対して、国語、算数の正答数を図ったところ、体力合計点の高かったグループは正答数も高く、体力合計点が低いグループは正答数が低いとの相関関係がわかりました。
勉強に運動はプラスの効果がある 勉強の効率を考えれば体を動かすことは大切

またアンダース・ハンセン氏の一流の頭脳という本では、運動と学力の相関関係がさらに詳しく書かれています。
スウェーデンのカロリンスカ研究所の研究によると、週に2回の体育の授業を受ける生徒と、毎日体育の授業を受ける生徒を比較した結果、毎日体育を受けている生徒の方が学力が高いことがわかりました。
運動の種類については、心拍数が1分間に最大150回まで上がる程度の運動であれば、ランニングだけでなくボール遊びなどの体を動かす活動も効果的だとされています。
体を動かすことが学習にも良い影響を与えると言われていますので、友達と遊んだり運動したいと感じた時には、体を動かすことが大切だとわかります。書籍によれば、10分から40分の息が上がる運動が推奨されているため、誰かと一緒でなくても、一人でウォーキングやランニングを楽しむのも良いでしょう。
受験勉強の合間に友達と遊ぶのは、リフレッシュにもなりますね。
学校の休み時間に体を動かして遊ぶのも、気分転換にぴったりです。
運動にはストレスを解消する効果もあるので、ぜひ取り入れてみてください。
ただし、遊びすぎや体の動かしすぎなどには注意してください。
運動しすぎて勉強の時に眠くならないように適度に運動をしましょう。
受験勉強に必要な「勉強体力」の付け方 少しずつ勉強で鍛える
この「勉強体力」は、運動に必要な体力と似たようなものです。運動をしていない人が急に42.195kmのフルマラソンを走るのは難しいことは、誰でも理解できるでしょう。42.195kmを走るためには、まず1kmから始めて、次に3km、5km、10km、15kmと少しずつ距離を伸ばしていくことが大切です。
「勉強体力」も同じで、最初は10分の勉強からスタートし、次第に15分、30分、45分、1時間と勉強時間を増やしていくことが必要です。
受験は体力勝負だよって言われてるのに体力無くてむりすぎ。
— は あ ち ゃ 。 🌙 (@hazuki___study) September 14, 2021
「勉強体力」の付け方 体力づくりは適度な睡眠、栄養、休憩が必要

勉強において体力をつけるためには、勉強時間だけでなく、睡眠や食事も非常に重要です。
42.195kmのフルマラソンを走る人たちの睡眠や食事を考えてみてください。
フルマラソンを走るランナーたちが、寝不足や栄養不足で挑むとは考えにくいですよね。勉強も同じことが言えます。
勉強のためには、睡眠時間や食事がとても大切です。
小学生は9時間、中学生は8時間、高校生は7時間半の睡眠が理想的です。
また、睡眠の質も重要なので、Sleep Meisterのようなアプリを使って良質な睡眠が取れているか確認するのもおすすめです。
良い睡眠を得るためには、22時から2時のゴールデンタイムを意識することが大切です。
そして休憩時間も非常に重要です。人間の集中力は約45分が限界とされているため、45分ごとに休憩を取ることをお勧めします。また、勉強を始めたばかりの時は、15分ごとに休憩を挟むのも効果的です。ベネッセの研究によると、15分の勉強を3回行ったグループは、60分連続で勉強したグループよりも117%も成績が良かったというデータもあります。
勉強を続けるためには「勉強体力」を養うことが大切です。そのために考慮したいのは「飽きない工夫」です。人間はどんなことでも飽きてしまうことが多いとされています。もし「この勉強はもう飽きた」と感じると、疲れを感じて勉強をやめたくなるかもしれません。そんな時は、気軽に他の教科に切り替えてみるのが良いでしょう。
体力の付け方鍛え方、戻し方 基礎体力があれば勉強にもプラスの効果
私は体力がないので受験を乗り切られるか不安という方に体力自体をつける方法も紹介をします。
最初のランニングは5分から増やしていく
体力をつけるにはランニングをオススメします。
理由としてはわかりやすく早く体力がつくからです。
最初は5分、それから体力に余裕が出るごとに10分、15分、20分と少しずつ走る時間を増やしましょう。
ただし注意点としましては、足首や膝を傷めないようにすることです。※ルームランナーを推奨
また走りすぎて睡眠時間が増えすぎないようにです。
最初の筋トレは10回から増やしていく
受験に不要そうな筋トレですが役に立つこともあります。
それは運動をしていない場合の脂肪のつきにくさとリカバリーできるスピードの差です。
受験に合格をした際は部活や遊びなどがひかえており筋肉を鍛えておいて損はありません。
腕立て伏せ、腹筋、背筋、スクワットなど家でもできる自重トレーニングで行いましょう。
急な筋肉痛にならないように週に2回程度割合で、回数は10回単位で増やしていきましょう。
今回は「体力」と「学力」の相関性と、「勉強体力」について紹介をしました。
毎日体を動かす体力のある人の方が学力も高い傾向にあることがわかりました。
運動自体ストレス発散になるので、遊びなどで体を動かすことはとても良いことがわかります。
受験勉強に必要な「勉強体力」はランニングで走れる距離と同じように少しずつ伸びるため、無理なく増やしていきたいですよね。
こちらの記事もオススメ
| Tweet |