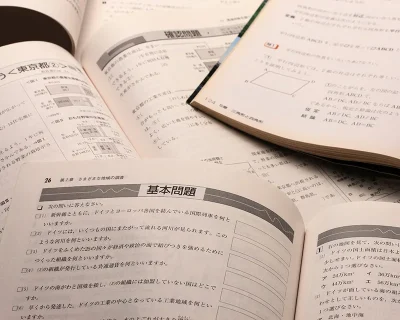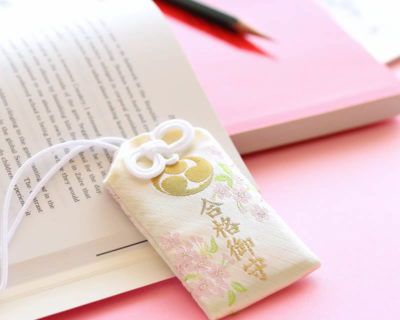小中学生の宿題は無意味!という論文は、本当?ウソ?
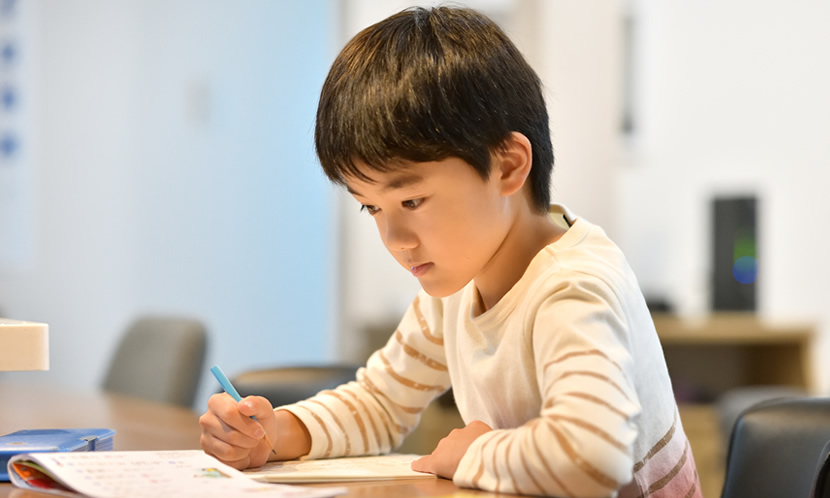
宿題が無意味だという報道や情報を耳にしたことはありますか?
宿題をしても成績に良い影響を与えないどころか、逆にやる気を失わせるという意見もあります。こうした情報をそのまま信じて「宿題を無理にやらなくても大丈夫」と考えるのは避けるべきです。なぜこのような「宿題不要説」が広まったのか、そして実際に宿題が効果的なのかを順を追って説明していきます。
- 目次
なぜ小中学生の宿題が無意味という噂が出たのか?週間事実報道とDaiGoさんから

まず、「週間事実報道」というメディアが「宿題は無意味だ」という記事を発表したことで、話題が広まりました。
その後 新聞などでも宿題が無意味であるという報道がされました。
また、メンタリストのDaiGoさんがYouTubeで「宿題が無意味であることが科学的には示唆されてる件【追加情報あり】」という動画を公開し、話題になりました。DaiGoさんはこの動画の中で、宿題について次のような意見を述べています。
・宿題を出す意味がない、宿題を出すことを禁止した方がいい
・小学生においては、宿題の効果がない
・成績が上がるという事実はない、むしろヤル気がなくなる
この動画は多くの議論を引き起こしました。DaiGoさんが引用したのは、デューク大学のハリス・クーパー教授の研究です。しかし、この研究に関してDaiGoさんが誤訳をしているのではないかという指摘もありました。真偽を確かめるために論文を探しましたが、元の論文は見つかりませんでした。ただし、論文の著者による別の記事を見つけたので、そちらを紹介します。
デューク大学と論文作者ハリス・クーパー教授は宿題を肯定している

デューク大学のハリス・クーパー教授が関わっている研究チームは、1987年から2003年にかけて宿題に関する60件の調査を分析しました。その結果、宿題は学生の成績に良い影響を与えると結論づけています。また、ハリス・クーパー教授自身も宿題について肯定的な見解を示しています。
・調査によると、幼い子供も含め、すべての子供は、学校の宿題を持ち帰ると、よりよく学ぶことができる
・宿題が成功する秘訣は、宿題の内容が生徒のレベルと合っていて家庭の状況に適していること
・また幼児の場合、宿題は短い時間で、自力で解けるものでなければならない
・宿題はまた、保護者に学校で何が起こっているかを見て、子供の学業上の長所と短所について学ぶ機会を与えることができる。
・宿題が適切に与えられている時は、それは良い薬のようなもの。少なすぎると効果がなく、多すぎると事態が悪化する可能性があり、適切な量で子供たちには良い効果を発揮する
・小学生が宿題をするのは、時間管理ができるようになるのと、勉強の習慣を身につける意味がある
このように述べています。
ただハリス・クーパー教授は、宿題が逆効果になることについて一つのポイントを挙げており、宿題が多すぎると成績が向上する傾向はないと指摘しています。
ハリス・クーパー教授によると、宿題の時間の目安としては、1学年につき10分ずつ増やすがよいとのことで、例えば小学1年生ですと10分/日、5年生ですと50分/日、中学3年生だと1時間半/日といった時間になります。
参照:DUKE STUDY: HOMEWORK HELPS STUDENTS SUCCEED IN SCHOOL, AS LONG AS THERE ISN’T TOO MUCH
参照:NEWS TIP: ‘HOMEWORK IS LIKE GOOD MEDICINE’ AND OTHER RESEARCH-BASED BACK-TO-SCHOOL ADVICE
宿題において注意する点を紹介 効果が出にくい宿題とは
論文では宿題においての注意点も紹介されています。
宿題の量が多すぎて時間がかかる
何事も量が多すぎると、始める前から大変だと感じることがありますよね。宿題は自分の意欲が求められるものなので、特に量が多いと時間や労力がかかると感じて、やる気を失ってしまうことがあります。小学生の低学年のうちは、宿題は「自分を管理すること」と「勉強の習慣を身につけること」を目的として取り組むことが大切です。
宿題のレベルが合わず自力で解けない問題がある
宿題があまりにも難しいと、終わらせることすらできず、取り組む気にもなれませんよね。宿題は復習の役割を果たしており、学校で学んだ内容を振り返ることで記憶を強化するためのものです。しかし、自分のレベルを超えた難しい問題では、復習の効果が薄れてしまいます。親に手伝ってもらったり、先生に個別に質問してわからない部分を減らすことが大切です。
簡単すぎて、解くことに意味がない問題がある
こちらは逆に宿題の難易度が低すぎるケースです。しかし、繰り返し行うことでより記憶に定着しますので、手を抜かない方が賢明です。自分にとって簡単すぎる問題が出た時は、さっと片付けるのが良いでしょう。
宿題をやらない子供の原因は◯◯が嫌いだから
学校に行く意味や理由を大人がキチンと解説したら…
改めて宿題は大切 宿題をするメリットを紹介

論文の作者も言うように、改めて宿題は良い効果があることがわかりました。
論文の著者が紹介した内容以外にも、宿題をする効果を紹介します。
授業の内容をもっと深く理解することができます。
例えば、マンガや映画でも2回目に観た時に気づくことありますよね?
これは勉強でも同じように起こります。
授業では、ハッキリとわからなかったことが、宿題をしている時に気づきキチンとした理解に繋がることがあります。
また授業で学んだことを宿題などで繰り返し学習することで、記憶により定着させることができます。
家での勉強を習慣化することができる
家での勉強は非常に重要です。中学、高校、大学と進むにつれて、学ぶ内容はどんどん難しくなります。授業中に聞くだけでは、短期間で覚えられることもありますが、長い目で見ると記憶に定着しません。だからこそ、しっかりと知識を身につけるためには、学習時間が必要です。これを補うのが家庭での勉強です。家での勉強を習慣にするためには、宿題がとても良いきっかけになります。受験勉強をする際には、学力を向上させるために勉強時間を増やす必要がありますが、宿題を通じて勉強を習慣化していれば、苦労せずに勉強に取り組むことができるでしょう。
自立心を養う
子供は成長するにつれて、自分で考え、選択する力が求められます。
どの学校に進みたいのか、そのためにどれくらい勉強しなければならないのかを考えることが大切です。また、受験勉強では、自分から進んで勉強に取り組む姿勢が重要です。誰も自分の代わりに勉強してはくれません。宿題は、自立した学びを促すための良い方法です。最初から親が全く関与しないのも良くありませんが、過度に干渉するのも避けるべきです。子供が自立して学べるようにサポートし、彼らの自立心を育てていきましょう。
今回の記事はいかがでしたでしょうか?
宿題が無意味でやらなくてもいいということはないと感じていただけたのではないでしょうか?もし宿題が本当に意味がないものであれば、学校や塾がそれを行うことはないと思いませんか?日々多くの情報が流れていますが、その情報をそのまま受け入れるのではなく、正しいかどうかを見極めることが大切です。特に常識を覆すような意見や発言には注意が必要です。メディアやYouTuberは、多くの人に見てもらうために情報を発信しますので、注目を集めるためにインパクトのある内容を選ぶ傾向があります。しかし、情報が正しいかどうかは調べなければわかりません。ですので、これまでの常識とは異なる情報が出てきた場合は、さまざまな意見や情報を集めて判断するようにしましょう。
こちらの記事もオススメ
| Tweet |