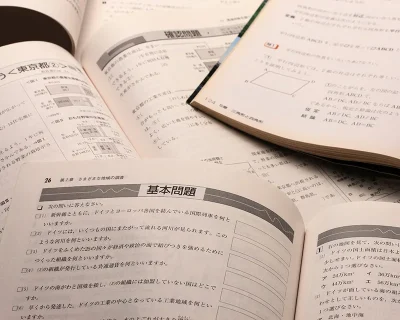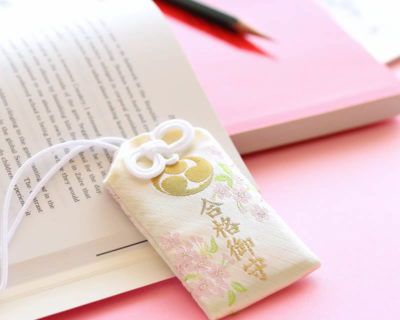勉強はアウトプットすると効率が上がる!すぐに実践できる方法を紹介

勉強において「アウトプットが重要」とよく言われますが、その効果について具体的にご存じでしょうか?
ある実験によると、アウトプットを行ったグループは平均80点、一方でアウトプットを行わなかったグループは35点という結果が出ました。
その差はなんと45点。アウトプットを取り入れることで、記憶の定着率が格段に上がり、勉強効率が大きく変わることが示されています。
この記事では、アウトプットの効果を裏付ける論文の内容と、日常ですぐに実践できる具体的なアウトプットの方法をご紹介します。
アウトプットの効果が明確にわかる!カーピック博士の実験

アウトプットの重要性を示す代表的な研究として、アメリカ・パデュー大学のカーピック博士による実験をご紹介します。
この実験では、学生に40個のスワヒリ語の単語を覚えさせた後、最初のテストを実施。その後、学習方法とテスト方法(インプットとアウトプット)を変えて、4つのグループに分け、一週間後に再テストを行いました。
※この実験での「インプット」は暗記、「アウトプット」はテストを意味します。
第1グループ
【インプット】すべての単語を再暗記
【アウトプット】すべての単語を再テスト
→ 結果:80点
第2グループ
【インプット】間違えた単語のみ再暗記
【アウトプット】すべての単語を再テスト
→ 結果:80点
第3グループ
【インプット】すべての単語を再暗記
【アウトプット】間違えた単語のみ再テスト
→ 結果:35点
第4グループ
【インプット】間違えた単語のみ再暗記
【アウトプット】間違えた単語のみ再テスト
→ 結果:35点
ここで注目したいのは、アウトプットの対象が「すべての単語」だったグループ(第1・第2グループ)が、どちらも80点を取っていたという点です。
一方で、誤答だけに絞ってテスト(アウトプット)を行った第3・第4グループは35点と、大きな差が生まれました。
これは、すでに覚えた内容であっても再度アウトプットすることが、記憶の定着にとって非常に効果的であることを示しています。
※ちなみに「テスト=アウトプット」とされるのは、覚えたことを思い出し、実際に書くというプロセスが含まれるためです。
アウトプットの大切さが、実験を通してはっきりと見えてきますね。
実際のインプットとアウトプットとは?

では、具体的に「インプット」や「アウトプット」とは、どんな行動を指すのでしょうか?
インプットの例:
-
授業を聞く
-
教科書を読む
-
先生の説明をそのままノートに書き写す
アウトプットの例:
-
テストを受ける
-
授業内容を人に説明する
-
先生の言葉をヒントに、自分の言葉を付け加えてノートに書く
-
習った内容を思い出して、要点をまとめて書き出す
アウトプットとは、インプットした情報を思い出して、自分の頭を使って表現する行為です。書くことでも、話すことでも構いません。重要なのは、「自分の思考を通して情報を出す」プロセスがあるかどうかです。
特に注目すべきなのが、「ノートを書く」という行為。
先生の板書をそのまま書き写すだけでは、アウトプットとは言えません。なぜなら、そこには自分の思考が介在していないからです。
では、どうすればノートをアウトプットとして活用できるのでしょうか?
それは、あとから自分のノートを見直したときに、授業内容がしっかり思い出せるかどうかで判断できます。
たとえば、1ヶ月前のノートを読み返して授業の内容がスッと理解できれば、それは良いアウトプットの証拠です。逆に、何を習ったか思い出せないようであれば、単なるインプットにとどまっており、アウトプット効果は不十分です。
このように、「自分の言葉で書く」「要点をまとめる」「思い出して再構成する」といった工夫が、アウトプット力を高め、記憶の定着にもつながります。
アウトプットできているノートの書き方とは?

アウトプットができているノートとは、その授業を受けていない人が見ても、授業の内容がある程度わかるノートのことです。
黒板の内容をただ書き写すのではなく、先生の話した内容や自分の考えたこと、感じたことも書き加えることがポイントです。たとえば、歴史の授業なら出来事の背景や先生が話したエピソード、自分なりの解釈などをメモすることで、記憶にも残りやすくなります。
ノート以外にもできるアウトプットの方法

・1. 誰かに説明してみる
人に説明することは、非常に効果的なアウトプットです。なぜなら、説明するには内容の理解が必要だからです。
うまく説明できない部分があれば、それが「自分が理解できていないポイント」だとわかります。友達に説明してみるのも良いですが、時間が取れない場合は、一人で「先生になったつもり」で授業をしてみる「エア授業」もおすすめです。
・2. ブログやSNSに授業内容を要約して投稿する
授業で学んだことを、自分なりにまとめて発信することもアウトプットになります。ブログやSNSに書くことで、思い出しながら整理する練習にもなりますし、同じように学んでいる人から共感やコメントをもらえることもあるかもしれません。
ただし注意したいのは、「いいね」や「コメント」といった反応に振り回されないことです。目的はあくまで学習内容の定着なので、SNSは手段として割り切って使うことが大切です。
アウトプットの精度を上げるために
アウトプットとしてのノートをもっと効果的に活用するには、そのノートを誰かに見せてみるのも一つの手です。親や友達で構いません。
他人がノートを読んだときに「わかりづらい」と感じた部分があれば、それは自分の理解が浅かったり、書き方に工夫が必要な部分です。その箇所を見直して書き足したり、整理し直すことで、アウトプットの質がどんどん高まっていきます。
勉強のアウトプットが苦手な人へ──まずは「好きなこと」で練習を

「アウトプットが大事なのはわかったけど、正直めんどくさい…」
そう思ってしまう方も多いのではないでしょうか?
実際、アウトプットは「ただ聞いて覚える」よりも、
・集中して話を聞く
・内容を理解する
・自分なりに整理する
・言葉にして伝える
という複数の工程が必要なので、インプットだけよりずっと頭を使います。
そのぶん大きな効果があるのですが、「やるぞ!」と気合が必要なのも事実です。
そこでおすすめなのが、勉強の前に「自分の興味があること」をアウトプットする練習です。
たとえば、好きなアニメや映画、ハマっているゲームやマンガ、推しのサッカー選手について――
そういった「語りたいこと」を、自分の言葉でまとめてみましょう。
ブログでも、SNSでも、ノートに書くだけでも構いません。
自分の気持ちを整理して伝えるという行為が、自然とアウトプットのトレーニングになります。
まとめ:アウトプットは「記憶に残す」最強の手段
今回は、アウトプットの効果と具体的な方法について紹介しました。
アメリカ・カーピック博士の実験では、アウトプットを取り入れたグループは取り入れなかったグループより45点も点数が高かったという結果が出ています。
「暗記が苦手…」という人ほど、アウトプットの力を活かすべきかもしれません。
最初はハードルが高く感じるかもしれませんが、まずは自分の興味のあることから始めてみてください。
自分の言葉で表現しようとするだけで、脳がどんどん活性化されていきますよ。
効率よく、そして楽しく学ぶために、今日から少しずつアウトプットを取り入れてみましょう。
こちらの記事もオススメ
| Tweet |