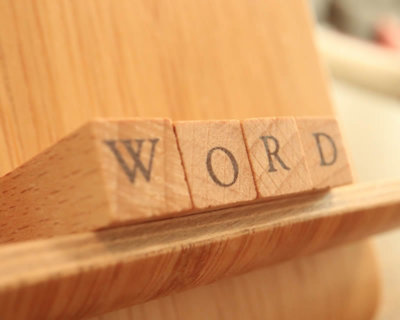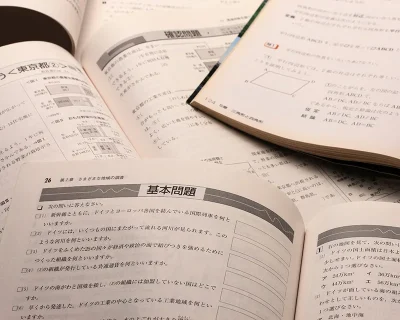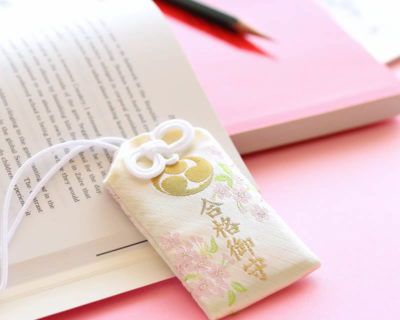学校に行く意味を考える|通う理由やメリットを教育学・論文から解説

近年、不登校のYouTuberとして知られるゆたぼんさんの発言が大きな注目を集めました。
その言葉は「学校に行かなくても大丈夫。」という、従来の常識を揺さぶるものでした。
実際、大人になった今でも「学校で学んだことは本当に将来に役立つのか?」「そもそもなぜ学校に通わなければならないのか?」と考えた経験がある方は多いのではないでしょうか。
歴史を振り返れば、有名大学や高校に進学していなくても素晴らしい業績を残した人は数多くいます。
さらに現代では、パソコンやスマートフォンを使えば知識や情報を即座に得られる時代です。そのため「学校で勉強する必要はないのでは?」という意見も一定数存在します。
この「学校に行かなくても大丈夫なのか?」というテーマは、X(旧Twitter)をはじめとするSNSでもたびたび議論になり、多くの人の関心を集めています。
※ゆたぼんさん自身は小学校の頃に不登校を経験し、その後中学3年生で登校・高校受験に挑戦しました。
とはいえ、子どもたちが抱く疑問に対して「子どもは学校に行くべきだ」や「大人になれば分かる」といった抽象的な答えでは納得できないことも多いでしょう。
実際に学生自身も「学校に通う意味」や「学校生活のメリット」について疑問を抱くことは珍しくありません。
そこで本記事では、論文や書籍、アンケート結果、さらにはひろゆきさんが語った学校に通う理由なども交えながら、学校に行く理由や意義、そして通うことで得られるメリットを詳しく解説していきます。
- 目次
学校に通えないことが深刻な問題となっている後進国・発展途上国

日本では、ゆたぼんさんのように「学校に行かない」という選択肢をあえてとるケースも話題になります。しかし世界に目を向けると、学校に行きたくても通えない子どもたちが数多く存在します。特に発展途上国や後進国では「学校に通えないこと自体が大きな社会問題」とされています。
なぜ学校に通えないことが問題なのかというと、次のような悪循環につながるからです。
1.教育を受ける機会を失う → 2. 選べる仕事が限られる → 3. 収入が低く生活が苦しい → 4. 貧困から抜け出せず、次の世代へと連鎖する
貧困と聞くと、日本では実感しにくいかもしれません。しかし実際には「食べたいものが食べられない」「栄養不足で体調を崩しやすい」「病気になっても治療を受けられない」「安全な住まいを確保できない」「行きたい場所へ行けない」「欲しいものが買えない」といった、基本的な生活の自由さえ失われてしまう状況を指します。つまり、教育を受けられないことがそのまま「生き方の制約」につながってしまうのです。
一方で教育を受けることができれば、状況は大きく変わります。学校に通うことで知識やスキルを身につけ、より安定した職業を選べるようになり、生活水準や人生の選択肢が広がっていくのです。
教育を通じて職業選択の幅が広がれば、収入も増え、栄養のある食事を取れるようになります。「欲しいものを買える」「安全で快適な家に住める」「旅行や娯楽を楽しめる」など、日常生活の質そのものが向上します。つまり、学校に通えるかどうかが「豊かな人生を送れるかどうか」の分かれ目になるのです。
さらに教育の効果は一代限りではありません。学んだ親は自分の子どもにも教育を受けさせることができ、その子どももまた自分の将来を自由に選べるようになります。こうして貧困の連鎖を断ち切り、世代を超えて豊かな生活を築いていけるのです。
発展途上国や後進国において、教育は「生活を根本から変える力」を持ち、社会全体の未来を左右する重要な要素なのです。
日本は先進国。学校に行く理由や義務教育の本当の意味とは?

大人に「なぜ学校に行かなければならないのか?」と聞くと、多くの人は「小学校や中学校は義務教育だから」と答えるでしょう。
しかし、これは少し誤解があります。実は義務教育とは「子どもに通学義務がある」という意味ではなく、保護者に子どもを学校に通わせて教育を受けさせる責任があることを指しています。
つまり義務教育の本質は、「子どもには教育を受ける権利がある」ということです。
そのため、子ども本人が「学校に行かない」と決めても罰則はありません。とはいえ、権利を放棄することは自分の将来の可能性を狭めることにつながります。
罰則がないからといって「学校に行かなくてもいい」と考えてしまうかもしれませんが、実際には学校に通うことが自分の未来をつくる大切な一歩です。先進国である日本の社会は「教育を受けること」を前提に成り立っており、その中で学校は欠かせない役割を果たしています。
前の章で述べたように、教育を受けられない国では貧困の連鎖が深刻な問題です。一方で日本のような先進国では、教育を受けることが当たり前であり、その学びが将来の社会参加や職業選択を支えているのです。
実際に求人情報を見ると、「応募資格は高校卒業以上」「大卒以上」といった条件が並んでいます。
これは会社で働くための最低条件であり、応募条件を満たさなければ面接に進むことすらできません。つまり学歴や資格は社会での入り口を広げるための鍵となるのです。
日本では、学歴によって「選べる仕事の幅」が大きく異なります。求人情報サイトやハローワークを見比べると、中卒・高卒・大卒で選べる職種の数や内容が明確に違うことがわかります。
さらに、教師や医師、薬剤師など特定の仕事に就くためには大学や専門課程を修了し、国家資格を取得することが必要です。
もちろん「やりたい仕事」が明確にある場合は、その職業に必要な学歴や資格を調べて計画的に進学や勉強を進めることができます。
しかし多くの子どもは将来やりたいことがまだ定まっていませんし、そもそも社会にはどんな仕事があるのかを知らない段階です。さらに、AIや自動運転などの技術革新によって、今ある仕事が10年後にはなくなる可能性もあります。
(例:かつて存在した「ワープロ専用オペレーター」という職業は、今ではほぼなくなっています。)
だからこそ、将来の可能性を広げるために「まず学校に行っておくこと」が重要です。
選べる仕事の数ややりがいのある仕事に出会える確率は、学び続けることで大きく高まります。
子どもの頃には、自分にどんな仕事が向いているのかを正確に判断するのは難しいものです。
だからこそ、今は「将来の選択肢をできるだけ広げておく」ことが一番大切。
その第一歩が「学校に行くこと」なのです。
学校に行くことで得られる知識と基礎学力の重要性
学校での勉強を通じて身につける知識は、将来社会で働き、自立して生活していくために欠かせない土台です。
たとえば、本やインターネットから情報を得ようとしても、まず漢字を読めることや国語の基礎力がなければ理解ができません。
確かにインターネットは便利なツールですが、普及してからまだ数十年しか経っておらず、今でも多くの専門知識や研究成果は書籍にしか載っていないこともあります。
さらに国語力は、人と円滑にコミュニケーションを取るために必要不可欠ですし、給料や生活費の計算、日常的なお金の管理には算数の力が必要です。
つまり、学校で学ぶ基礎学力は「日常生活」と「将来の仕事」の両方を支える力になるのです。
また学校で習う基礎的な知識がなければ、より高度な学習を理解することは難しいでしょう。
例えばAIシステムを構築したい場合、プログラミングスキルの習得には英語の理解が必要ですし、数学の微分積分・確率・統計といった応用的な知識も欠かせません。基礎がなければ、その先の専門分野に進むことはできないのです。
学校に通うことで、毎日4〜6時間というまとまった学習時間が自動的に確保されます。もし学校に行かずに同じだけの知識を身につけようとすれば、自分で計画を立て、教材を選び、学習時間を管理しなければなりません。これは大人でも難しいことですから、子どもにとってはさらに大きな負担となります。
特に小学校から中学校までの9年間は「学力の基礎」を固める時期です。この期間にしっかりと学校で学んでいるかどうかで、その後の学習能力や進路の選択肢に大きな差が生まれます。まだ幼い子どもたちが、自分一人で必要な教材を選び、効率的に勉強するのは非常に難しいのが現実です。
さらに費用面でも学校に通うメリットは大きいといえます。公立の小中学校は義務教育であるため授業料は無料に近く抑えられていますが、学校に通わず塾や家庭教師で学ぶとなれば、大きな費用が発生します。
この点からも「学校に行くことは最も効率的に知識を得る方法」といえるでしょう。
勉強をする意味がわからなくなったら偉人の言葉が胸に響くかも
エッ!小中学生の宿題は無意味!?
学校に行く理由は「社会性」や「コミュニケーション能力」を育むため

学校は勉強をする場所であると同時に、人との関わりを通じて「社会性」や「コミュニケーション能力」を育てる場でもあります。
教室では同級生と、休み時間や部活動では先輩・後輩と、そして授業や行事では先生方と交流する機会が数多くあります。こうした人間関係の中で、子どもは自然と協調性や礼儀を学んでいきます。
日々の学校生活では、友達と協力して課題に取り組んだり、ルールを守って活動したりする経験を重ねます。
「決められた時間に行動する」「約束を守る」「周囲に迷惑をかけないようにする」といった基本的なマナーは、社会で生きていくうえで欠かせないスキルです。
なぜこれらの社会性や協調性が重要なのかというと、将来働くことになる会社や組織でも同じ力が求められるからです。
勉強で得た知識や資格も大切ですが、社会で評価されるのは「人と円滑に関わり、信頼関係を築けるかどうか」という部分でもあります。
例えば、仕事を依頼されたときに責任を持って対応できるか、決められた期限を守れるか、周囲の人を思いやりながらチームで成果を出せるか。
学校生活の中で培われる社交性や協調性は、そのまま社会人として必要とされるスキルにつながっています。
もちろん学校に通わなくても、家庭や地域活動、趣味のサークルなどで社会性を学ぶことはできます。
しかし学校は多くの子どもが同じ環境で集団生活を送り、自然に人間関係を学べる最適な場所です。社会は人と人との協力で成り立っているため、こうしたスキルを身につけることは将来にとって非常に大きな財産になるのです。
学校に行かないときは?──代わりに学力や社会性を身につけられる場を探そう
ここまで学校に行く理由は「基本的な学力・社会性・コミュニケーション力を育むこと」だと説明してきました。
逆に言えば、これらのスキルが身につけられるのであれば、必ずしも学校という形にこだわる必要はありません。
実際、不登校の子どもたちの中には、転校・通信制高校・フリースクールなどの別の学びの場を選ぶケースも増えています。
人間関係や学校の雰囲気が合わないこともあるでしょう。「全員が自分の学校を好きになれるわけではない」というのは自然なことです。
しかし、フリースクールに通ったことで「小中学校では勉強が楽しくなかったのに、転校後は学ぶのが楽しくなり、大学進学につながった」という事例もあります。
また、今はインターネットで全国の教育機関や学びの場を調べることができます。
気になる方は「住んでいる都道府県+フリースクール」で検索してみると、思いがけず自分に合った居場所が見つかるかもしれません。
学校に行くメリットとデメリットを整理してみよう
次に、学生の視点から学校に通うメリットとデメリットをまとめてみます。
「学校に行く理由」を理解するには、プラス面とマイナス面の両方を把握しておくことが大切です。
時間を守る習慣が身につく【学校に行くメリット】
毎朝決まった時間に起きて通学し、時間割どおりに行動することは、自然と時間管理能力を育てます。
この習慣は学生生活だけでなく、社会人として働くときにも役立ちます。
友達ができる【学校に行くメリット】
授業や部活動を通じて気の合う友達ができるのも学校の魅力です。
友人との関係は家族とは異なる特別なもので、同年代ならではの絆や安心感を得られます。
仲間との会話で心が軽くなる【学校に行くメリット】
友達やクラスメートと話すことで、自分の気持ちを共有し、共感を得られます。
不安や落ち込みを一人で抱えるより、誰かに話すことで気持ちが軽くなり、精神的な支えになります。
協調性が育まれる【学校に行くメリット】
運動会や文化祭、合唱コンクール、掃除など、学校には共同作業の場がたくさんあります。
みんなで協力して取り組む経験を通して、自然と協調性やチームワークを身につけることができます。
デメリットもあるが社会で役立つ力になる
一方で、学生が感じるデメリットもあります。
例えば「好きではない教科も勉強しなければならない」「自由時間が少なくなる」「遅刻しないために早起きが必要」といった点です。
しかし、これらは社会に出ても避けられない現実です。
苦手なことにどう向き合うか、決まった時間に行動するかは、どの職業にも共通して必要なスキル。学校はそれを練習できる場でもあるのです。
ひろゆきさんが語る「学校に行く理由」
有名人の意見は、多くの人にとって説得力があり、学校に通う意味を多面的に考えるきっかけになります。
実業家のひろゆきさんは「同年代の友達ができること」こそが学校に行く大きな意義だと語っています。
大人になると、お金や仕事が人間関係に影響を与えることが多くなります。しかし小学校・中学校・高校の時期は、お金ではなく『一緒にいるだけで楽しい』という理由で友達をつくれる、人生で特別な時間だと強調しています。
また、大学以降はいくらでもやり直しが可能ですが、小中学校の経験は「同じ年齢でしか味わえない一度きりの体験」であり、その時期を逃すと取り戻せないと指摘しています。
さらに、友達やクラスメートとの関わりを通じてコミュニケーション能力を育むことの重要性も語っています。
例えば、喧嘩をした後に仲直りをする経験や、人間関係の摩擦を解決する経験は、社会に出てからも大きな財産になるというのです。
中高生アンケート「学校は楽しい?」
ここでご紹介するのは、中高生を対象に行われた「学校生活は楽しいか?」というアンケート調査の結果です。
「とても楽しい」「まぁ楽しい」と答えた生徒は全体の約9割に達しました。その理由として最も多かったのは、やはり友達の存在です。
一方で、約1割の生徒は「あまり楽しくない」「全然楽しくない」と答えており、学校に行くことに対してポジティブに感じていない人が一定数いることもわかります。
「学校に行きたくない」と思う気持ちは、決して珍しいことではないのです。
高校に入学した理由に関するアンケート
さらに、高校生に対して「なぜその高校に入学したのか?」を調べたアンケート結果もあります。
- 46.9%:自分の学力に合っているから
- 21.8%:資格取得が可能だから
- 21.6%:やりたい部活動があったから
- 20.7%:就職に有利だから
- 17.3%:通学が便利だから
このように、約2割の高校生が資格取得や就職を意識して学校を選んでいることがわかります。
「部活動を楽しみたい」「進学や就職に役立てたい」といった多様な動機があることからも、学校は単に勉強の場ではなく、将来を見据えた選択肢を広げる場であることが読み取れます。
日本の不登校児は2019年度で18万1272人。海外の事情との違いとは?
日本における不登校児の数は年々増加しており、2019年度には過去最多の18万1272人に達しました。
内訳は小学校で5万3350人(在籍児童の約0.8%)、中学校で12万7922人(在籍生徒の約3.9%)です。
年齢が上がるほど不登校の割合も高くなり、その背景には「無気力や不安」「友人関係のトラブル(いじめを除く)」「親子関係の課題」などさまざまな要因が挙げられています。
一方で海外の状況を見てみると、オランダやフィンランドにも不登校の子どもは存在しますが、日本とは考え方が大きく異なります。
日本では「学校に行けない=よくないこと」と捉えられがちですが、オランダやフィンランドでは「子どもに合った学びの場を探せばよい」という考え方が主流です。
実際に、フリースクールやオルタナティブスクールに通うことも正規の出席として認められており、公立学校と組み合わせて通うことも可能です。
例えば「週3日は公立学校、残り2日はフリースクール」という柔軟なスタイルが制度として認められています。
こうした仕組みは、ジェンダーレスの考え方と同様に「多様性を尊重する教育のあり方」といえるでしょう。
日本でも同じように柔軟な学校制度や選択肢が広がり、誰もが自分に合った学び方を選べるようになることが望まれます。
参照: 時事ドットコム 「小中不登校18万人 過去最多、7年連続増―文科省・問題行動調査」
参照: フィンランドの学校に行こう 「海外に”不登校”という概念は存在しない?」
学校に行く意味とは?──論文や教育学から5つの視点で考える
「なぜ学校に行かなければならないのか?」という問いは、子どもだけでなく大人にとっても普遍的なテーマです。
学校に通うことは当たり前のように思えますが、その本当の意味や価値を深く考える機会は意外と少ないかもしれません。
この記事では教育学や社会学の理論をもとに、学校に行く理由や学校に通う意味を5つの視点から整理してみます。
1. 知識・技能の習得(アカデミックな学び)
学校の基本的かつ最も重要な役割は、読み書きや計算といった基礎学力を習得し、社会・科学・歴史など幅広い知識を体系的に学ぶことです。
つまり、学校は「知の基盤」を築く場であり、人生のあらゆる選択に必要となる学力の土台を提供しています。
哲学者のジョン・デューイ(John Dewey)は著書『Democracy and Education』(1916年)で「学校は社会的経験を共有し、個人を育てる場」であると述べています。単なる暗記ではなく、生活に根ざした学びの体験を通して成長していくことこそが教育の本質だと説いています。
2. 社会性の育成(集団生活と人間関係)
学校生活では、クラスや部活動などの集団活動を通じて協調性やコミュニケーション力を育むことができます。
これは「非認知能力」と呼ばれ、テストの点数とは直接関係しないものの、将来の人間関係やキャリアの成功に深く関わる力です。
1966年に発表された「コールマン報告(Coleman Report)」では、学力に大きな影響を与えるのは授業だけでなく、家庭環境や友人関係といった「社会的要因」であると指摘されました。さらにOECDのPISA調査(2015)では、社会性や感情の安定が学力や幸福感に結びつくと報告されています。
3. 資格取得と社会的地位の獲得(学歴の役割)
現代社会において、学歴は進学や就職の条件、収入や社会的評価に直結することが少なくありません。
学校に通うことは、将来の進路やキャリアの選択肢を広げる「資格取得」の場であり、人生における大きな基盤となります。
社会学者ランダル・コリンズ(Randall Collins)は「Credentialism(資格主義)」という概念を提唱し、学歴は本質的な能力以上に「社会が認めた証明書」として機能すると指摘しました。また、ピエール・ブルデュー(Pierre Bourdieu)は教育が文化資本の差を拡大し、社会階層を再生産する仕組みでもあると論じています。
4. 自己実現と価値観の形成
学校は単なる勉強の場ではなく、「自分がなりたい姿」や「人生で大切にしたい価値観」を見つける場でもあります。
多様な教科、部活動、友人や先生との出会いを通じて、個々の興味や才能を発見し、進路や自己実現へとつなげていくことができます。
心理学者エリク・エリクソン(Erik Erikson)は青年期を「アイデンティティの確立期」と位置づけ、学校生活が自己形成に大きな影響を与えると述べました。また、キャロル・ドゥエック(Carol Dweck)の「成長マインドセット」理論も、努力や挑戦を前向きにとらえる力を育て、自己肯定感を高めることにつながります。
5. 福祉・安全・ケアの役割
現代の学校は学習の場であると同時に、子どもたちの生活を支える「セーフティネット」としての機能も果たしています。
特に家庭環境が厳しい子どもにとっては、学校が給食による栄養の補給、定期的な健康チェック、スクールカウンセラーによるメンタルケアなどを提供する大切な居場所となっています。
日本では養護教諭やスクールカウンセラーの制度が整備され、学校は「安心できる居場所」としての役割を強化しています。教育と福祉が密接に結びついているのは現代社会ならではの特徴といえるでしょう。
このように、学校に行く理由や意味は一言で語れるものではなく、多面的な価値を持っています。
- 知識・技能の習得(論理的思考や基礎学力の定着)
- 社会性の育成(協調性・人間関係・非認知能力)
- 資格取得と学歴(将来の選択肢やキャリア形成)
- 自己実現(興味関心や価値観の発見)
- 福祉・安全(生活と心のサポート機能)
教育学や社会学の理論は、「なぜ学校に行くのか」「学校に通う意味は何か」という問いを考えるヒントを与えてくれます。普段は当たり前に感じる学校生活も、実は人生や社会に深く関わる大切な意味を持っているのです。次の章では、さらに具体的にわかりやすくその意義を紹介していきます。
改めて考えると、小学校や中学校での学びは義務ではなく「権利」です。
学校に行く理由は、そこでしか得られない知識・学力・社会性・コミュニケーション力を育むためです。
ただし、学校に行けない事情がある場合には、フリースクールや支援プログラムなど代わりとなる学びの場を活用することも可能です。
不登校やいじめで苦しんでいる子どもにとって、無理に通学する必要はありません。重要なのは「どんな環境で学び、どう成長できるか」ということです。
やがて子どもは大人になり、自分の力で働いて生きていかなければなりません。
そのためには、基礎学力をつけ、社会性を身につけ、仲間と協力する力を養うことが大切です。
どんな職業に就くにしても、やりがいを感じ、自分の欲しいものを手に入れ、行きたい場所へ自由に行けるようになることが、幸せな人生につながるでしょう。
学校での学びや経験は、すべて「自分自身の未来のため」。学校に行く意味を考えることは、より良い人生を選ぶための第一歩なのです。
こちらの記事もオススメ
| Tweet |