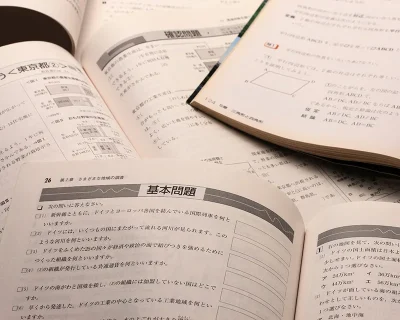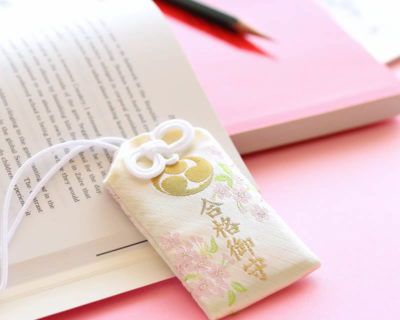子どもに怒ってしまうのはなぜ?子育てイライラの理由と対処法

子育てをしていると、毎日のようにイライラしてしまう…そんな経験はありませんか?
そして夜、寝顔を見ながら「今日も怒ってばかりだったな…」と自己嫌悪に陥ることもあるでしょう。
朝から晩まで子どもの世話をするのは、決して楽なことではありません。
ベビーシッターや保育士という職業があるように、子育ては立派な“仕事”とも言えるほどの重労働です。
さらに、子どもに社会で生きていくための知識・マナー・スキルを教える必要がある一方で、
子どもはまだ未熟な存在。思うように行動してくれず、反発したり言うことを聞かなかったりすることも日常茶飯事です。
そんな時、つい感情的に怒ってしまい、「自分はダメな親かも…」と悩んでしまう人も少なくありません。
もちろん、子どもが危ない目にあいそうな時や、明らかに間違っている時には叱ることも必要です。
ですが、毎日のようにイライラして怒ってばかりいると、親自身も苦しくなってしまいます。
最近では「怒らない子育て」も注目されていますが、実際にやってみようとしても、現実はそう簡単ではありません。
「怒らないと決めたのに、また怒ってしまった…」と自己嫌悪に陥ることもあるでしょう。
一体どんな子育てが“正解”なのか?
その答えが見えず、ストレスをため込んでしまい「育児ノイローゼになりそう」と感じる方もいるかもしれません。
そこで今回は、
-
怒る子育て vs 怒らない子育てのメリット・デメリット
-
イライラを少しでも軽減するための実践的な対処法
この2点を中心に、子育てに悩むあなたのヒントになる内容をお届けします。
こちらの記事もオススメ。子供の好き嫌いが多くて悩んだら。
こちらの記事もオススメ。中学生から子供の成績が落ちる??
- 目次
なぜ子育て中にイライラしすぎてしまうのか?怒りすぎてしまうのか?
子どもに対して、どうしてこんなにイライラしてしまうのだろう――。
その理由の一つとして挙げられるのが、「自分自身がそう育てられてきたから」という背景です。
たとえば「泣いてばかりの子どもに腹が立つ」「同じことを何度も言わせるなと思ってしまう」「のんびりしている姿にイラつく」…
これらは、あなたが子ども時代に親から受けてきた言葉や態度と深く関係していることがあります。
そしてその親もまた、自分の親――つまりあなたの祖父母から同じように育てられていたかもしれません。
つまり、怒りのパターンは無意識のうちに“引き継がれている”可能性があるのです。
だからこそまず大切なのは、自分が「どの場面で」怒ってしまうのか、そのポイントを客観的に把握することです。
そして、怒りのポイントが見えたら、過去のあなた自身にも目を向けてみてください。
小さな体で、厳しい親の言葉にも負けずに頑張ってきたあなた自身を「よくやってきたね」と認めてあげましょう。
今、あなたの目の前にいる子どもも、かつてのあなたと同じように、小さな体で一生懸命に日々を生きているということに気づくことができるかもしれません。
怒りすぎると、子どもにどんな影響があるのか?

子どもが何度も同じ失敗を繰り返したり、教えたことを全然やってくれないと、つい感情が高ぶって怒りすぎてしまうことがあります。
特に、他人に迷惑をかける行動や、怪我につながるような行動には、ある程度きちんと叱る必要もあるでしょう。
ですが、怒るという行為は、大人が思っている以上に子どもの心に大きな影響を与えるということも覚えておいてください。
特に母親は、子どもにとって絶対的な存在です。
「お母さんに喜んでもらいたい」「認めてほしい」と思っている子どもにとって、怒られることは大きなダメージになります。
度重なる叱責によって、「どうせ認めてもらえない」「愛されていない」と感じるようになると、
子どもの自己肯定感は低下していきます。
自己肯定感とは――
「自分は大切にされている存在だ」と感じる気持ち、
「このままの自分でいい」と思える土台です。
もし怒られてばかりの毎日になってしまうと、子どもは次第に…
-
嘘をついて自分を守る
-
物事に無関心になる
-
やる気をなくす
-
周囲に対して反抗的になる
といった行動が出てくる可能性もあります。
こうした状態が続けば、将来的に社会で生きていく力にも影響が出てしまうかもしれません。
また、親自身も「怒ること」が習慣になってしまい、子どもが少しでも言うことを聞かなければ怒る――という“負のループ”に陥る可能性もあります。
「怒らない子育て」のメリットとデメリット
こうした悪循環を避けたいと考えて、「怒らない子育て」を実践している親も増えています。
テレビや育児書でもよく紹介される考え方ですよね。
たしかに、感情的に怒らないことには大きなメリットがあります。
しかし、まったく怒らずに何も注意しない子育てには、デメリットもあるということを知っておくべきです。
たとえば、子どもが…
-
好きなだけ遊んで時間を守らない
-
他の子の物を勝手に使う/取る
-
人を叩く、蹴る
-
公共の場で迷惑行為をする(例:電車で寝転がる)
…といった行動をしても、親が何も言わなければ「これでOKなんだ」と学習してしまいます。
子どもは、何が良くて、何がいけないのかを自分で判断することができません。
だからこそ、親が言葉で伝え、体験を通して教える必要があるのです。
もし、それがないまま子どもが成長すると、他人への配慮やマナーを知らず、トラブルを起こしたり孤立するリスクも高まります。
「怒らないこと」はやさしさのようでいて、正しいことを教えない“無関心”にもつながりかねない――
この点はしっかりと心に留めておきたいところです。
怒ることも大切。でも「怒りすぎ」は親を苦しめてしまう

子どもに対して怒るのは必要なことです。
しかし、毎日のように怒ってばかりでは親自身も疲れ果ててしまう…そんな実感を持っている方も多いのではないでしょうか。
実際、怒るという行為にはエネルギーが必要で、精神的にも消耗します。
だからこそ、本当に必要な場面だけに怒りを使うために、「無駄な怒り」を減らすことが大切です。
振り返ってみると、「あれって怒るほどのことだったかな」と思う場面は意外と多いもの。
そこで、日常の中で意識するだけで怒りがグッと減るポイントを以下にまとめました。
怒りを減らすためにできること
-
出かける前は時間に余裕を持つ
バタバタしていると些細なことでもイライラしがちです。早めの準備で心にゆとりを。 -
おもちゃや本が壊れるのも成長の一環だと捉える
確かに壊れたら悲しい。でも、子どもが手加減や大切に扱うことを学ぶ過程でもあります。 -
触ってほしくないものは、手の届かない場所に置く
壊されたくないもの、大切なものは見えない場所へ。「触るな!」と怒る前に、環境を整えることも有効です。 -
壊されてしまったときは、「管理できなかった自分にも原因がある」と受け止める
責める前に少しだけ視点を変えると、感情が落ち着くこともあります。 -
子どもは一度言われてすぐにできるわけではないと知っておく
何度も失敗しながら学ぶのが普通です。できないことが前提で考えると、気持ちが楽になります。 -
上の子が下の子に意地悪してしまうのは自然なこと
「親の愛情を取られた」という不安からくる嫉妬が原因です。責める前に気持ちに寄り添ってみてください。 -
「他の子みたいになってほしい」と思わない
よその子と比べると、イライラの原因になります。あなたの子にはその子の良さがあります。 -
人は間違えて覚えるもの。子どもも同じ
間違えながら少しずつ成長するのが人間です。完璧を求めすぎず、プロセスを見守る気持ちを。 -
年齢ごとにできること・できないことがあると知る
今の年齢で「普通にできること」は限られています。成長の段階を理解することが、怒らないコツになります。
子どもに対して怒りすぎてしまうのは、「できて当然」という期待が無意識に高くなっていることも原因の一つです。
でも、はじめから何でもできる子なんていません。
何度も失敗しながら、教えられながら、ゆっくりとできることを増やしていくのが子どもなのです。
親の側も、自分の「当たり前の基準」を見直すことで、必要のないイライラから少しずつ解放されていきます。
イライラから解放されるかもしれない5つの方法
子育て中、「イライラが止まらない…」と悩んでいませんか?
頭では「怒らないようにしよう」と思っていても、感情が抑えられないこともあります。
そんなときは、自分の中で思っていることと本心がズレている可能性も。
ここでは、イライラを軽減し、気持ちがラクになる5つの視点をご紹介します。
1. 実は“子どもへの嫉妬”かもしれないと疑ってみる
イライラの根本にあるのが、**「無意識の嫉妬」**というケースがあります。
たとえば、子どもの頃に自分が十分に愛されなかったという思いがある人ほど、「親に可愛がられている自分の子ども」を見て、心のどこかで嫉妬を感じてしまうことがあります。
この嫉妬に気づくだけで、感情がフッと和らぐことも。
大切なのは、「嫉妬していたんだな」と気づいて受け入れることです。責める必要はありません。
誰しも嫉妬する気持ちはあるものです。気にしすぎず、イライラを減らすきっかけにしていきましょう。
2. イライラの矛先は配偶者への不満?
育児のイライラが、実はパートナーへの不満からきているケースもあります。
「家事を手伝ってくれない」「育児に協力的でない」「無駄遣いが多い」などの不満が心の中に溜まり、それが子どもへのイライラとして現れてしまうのです。
特にワーキングマザーは、仕事・家事・育児と常に全力。休む間もない生活に疲弊しがちです。
そんな時こそ、家族全体で生活のバランスを見直すことが必要です。
負担の偏りを感じたら、夫婦でしっかり話し合いましょう。
また、「夫が子どもの味方ばかりする」という感覚も、見えないストレスの原因になることがあります。
「自分ばかり頑張っている」と思ったときは、その思いを素直に伝えてみることも大切です。
3. 白黒思考をゆるめてみる
「怒るのはダメ」「絶対に怒らない育児をしなきゃ」と極端に考えてしまうと、自分をどんどん苦しめてしまいます。
たとえば、「子どもに怒るのは100%悪いこと」と思っていれば、他人が怒っている姿を見ただけでもストレスになります。
そんなときは、まず「怒ってしまう自分を許す」ことが大切。
そう考えるだけでも、心に余裕が生まれます。
もちろん、イライラをそのままぶつけるのではなく、
子どもの気持ちを尊重しながら、必要な場面では伝わる言葉で注意するのがポイントです。
子どもはすぐに変われません。何度も教えながら、ゆっくり育っていくものだと考えましょう。
4. 子どもの年齢に見合った期待かどうかを見直す
「なんでこんなこともできないの?」と怒りたくなったとき、
その行動が本当に“年齢相応にできること”かどうかを考えてみましょう。
たとえば、5歳の子に「遊んだおもちゃをすべて完璧に片づけて」と求めるのは、少しハードルが高いかもしれません。
もし自分が子どもだった頃はどうだったか、ご両親に聞いてみるのもおすすめです。
「ああ、自分も同じように失敗してたんだ」と気づければ、子どもに対する見方もやわらぎます。
私が息子の子育てにしんどくなったり、イライラしちゃう時は殆どが「こうあるべきだ」と思っている。別に命に関わることではないのに、○○すべきと決めつけるからその通りにしなきゃと思ってしまう。自分のなおすところに気付けたので、次はそれを行動に移せたらハーゲンダッツを褒美とします。
— *イケメン自閉症せいくん*ブログ更新中* (@seikunnoouchi) November 23, 2021
5.子どもの気持ちを聞き、思い違いに気づく
子どもが何かイタズラや問題行動をしたとき、
「わざとやったんだ」「困らせるためだ」と思い込んでいませんか?
でも実際には、子どもなりの理由や好奇心があっただけ、ということも少なくありません。
まずは、「なぜそうしたの?」と子どもの気持ちをしっかり聞いてあげることが大切です。
そして共感した上で、「なぜそれが良くなかったのか」を
子どもに伝わる言葉で短く・わかりやすく説明するようにしましょう。
子どもは一度では理解できないことも多いため、
根気よく丁寧に繰り返すことがポイントです。
怒るべきか、怒らないべきか――答えは“バランス”
育児の中で「怒ること」「怒らないこと」のバランスに悩むのは当然です。
ただし、どちらか一方に極端になると、次のようなリスクがあります。
-
怒りすぎる:子どもの自己肯定感が下がり、自信を失う
-
怒らなさすぎる:ルールが身につかず、社会性が育たない
だからこそ、感情にまかせず「必要なときに、冷静に、わかる言葉で伝える」ことが大切です。
そして何より、親自身が疲れ切らないようにすることが最優先です。
夫婦で協力し、育児の負担を見直し、イライラのもとを一つひとつ減らしていきましょう。
こちらの記事もオススメ
| Tweet |