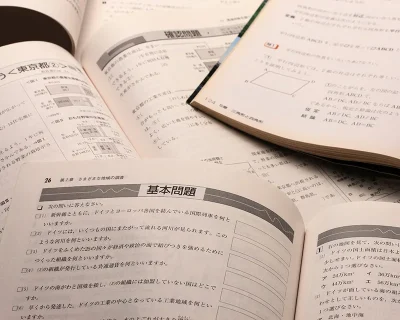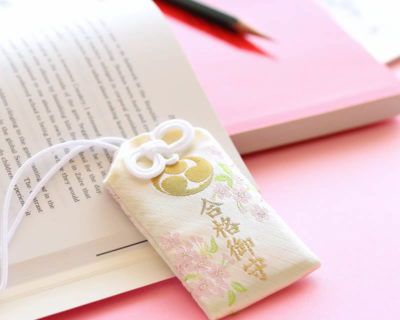中学受験の偏差値(愛知、岐阜、三重県)の活用方法と志望校判定の見方
シリーズ私立中講座

一般的に、高校受験や大学受験を行う際の学力をはかる指針として「偏差値」が使われていますが、中学受験を行う際にも偏差値を参考に生徒の学力を判断して志望校の決定などを行います。ここでは、中学受験における偏差値の概要、偏差値の活用方法と志望校判定の見方について解説します。
- 目次
偏差値の概要
偏差値とは
偏差値は、厳密に分けると「学力偏差値」と「学校偏差値」の2種類あります。
| 偏差値 | 概要 | 主な用途 |
|---|---|---|
| 学力偏差値 | ・母集団の平均点を50とし、そこを起点に、受験生の得点が全体のどの位置にいるかを見る ・25~75の範囲で算出 |
・受験生の実力を相対的に判断するものさし |
| 学校偏差値 | ・中学校や高校の合格難易度の差を示したもの ・模試の結果や入試結果を元に、大手学習塾などがカテゴライズ |
・志望校を決定する際の参考値 |
学力偏差値とは、模試を受けた受験生全員(母集団)の平均点を偏差値50と換算し、そこを基準に、受験生それぞれの得点が全体からどの位置にいるのかを示す数字です。中学受験や高校受験、大学受験の際に、生徒の実力を相対的に判断する「ものさし」として広く使用されています。
学力偏差値は、基本的に25~75までの範囲で算出されます。例えば、ある模試を受けた際、自分の点数が平均点と同じであれば学力偏差値は50になります。平均点から高い場合は、どのくらい高いかにより51~75の間、平均点より低い場合は、どのくらい低いかにより49~25の間でランク付けされることになります。
学校偏差値は、新規入学者を募集する複数の中学校・高校・大学の合格難易度の差を示したものです。大手学習塾や予備校などが、受験生を対象に開催した模試の結果や実際の入試結果を元に算出しカテゴライズしたものになります。
一般的に、どちらも「偏差値」とだけ言うことが多く、それが「学力偏差値」を指すのか「学校偏差値」を指すのかは文脈により異なりますが、明確な違いを説明する場合以外で言い分けることはほとんどありません。
偏差値を求めるには
偏差値を求める計算式は、
「(得点-平均点)÷ 標準偏差×10+50=偏差値」
になります。
こちらの計算式を用いることで、(学力)偏差値を自分で算出することが可能です。その場合、「平均点」と「標準偏差」を先に求めておく必要があります。平均点は、受験者の全員の得点を合計し、受験者数で割ったものです。
標準偏差は、「対象データのバラつきの大きさを表す指標」のことです。平均値からのばらつき具合が大きいと標準偏差も大きくなり、ばらつきが小さいと標準偏差は0に近づきます。標準偏差は平均値と組み合わせることで、対象データから抜き出した特定のデータが「どのくらい優れている、もしくは劣っているのか」の判断を下すときに活躍します。膨大な量のデータを分析する際に、データを正しく把握するために用いられる統計学の基本です。
標準偏差の求め方
試験の標準偏差を求めるには、以下の手順で計算します。
1. 平均点を求める
2. 偏差(得点-平均点)を求める
3. 分散(偏差を2乗した数値の平均)を求める
4. 分散の正の平方根を計算する
それでは、実際に計算していきましょう。
1.平均点を求める
平均点は、試験の受験者全員の得点を合計し、人数で割ると求められます。
以下のような結果の出た模試があったと仮定して、計算を行います。
表1
| 受験者 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
(100+80+60+40+20+10+30+50+70+90)÷10(受験者数)= 55
この場合の平均点は55点です。
2. 偏差を求める
偏差は、「得点-平均点」で求めます。
表2
| 受験者 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 平均点 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 偏差 | 45 | 25 | 5 | -15 | -35 | -45 | -25 | -5 | 15 | 35 |
3. 分散を求める
偏差を2乗し、その平均値を出します。
表3
| 受験者 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 |
| 平均点 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 偏差 | 45 | 25 | 5 | -15 | -35 | -45 | -25 | -5 | 15 | 35 |
| 上の2乗 | 2025 | 625 | 25 | 225 | 1225 | 2025 | 625 | 25 | 225 | 1225 |
偏差の2乗を足し、10人で割ります。
(2025+625+25+225+1225+2025+
625+25+225+1225)÷10=825
4. (正の)平方根を出す
825の平方根を出すと、「28.7228」になります。これが「標準偏差」になります。
学力偏差値の求め方
さて、偏差値を求める計算式は、「(得点-平均点)÷ 標準偏差×10+50=偏差値」でしたが、これを使って実際に、最高点を取ったAさん、最低点を取ったFさんの偏差値を計算してみます。標準偏差は28とします。
Aさん:(100-55)÷28×10+50=66.0
Fさん:(10-55)÷28×10+50=33.9
Aさんは偏差値66、Fさんは偏差値33.9と算出されました。
基本的に、自分で偏差値を算出するのは大変です。塾で行う模試では、試験結果のデータに偏差値が必ず載っていますので、自分で偏差値を出そうとしなくても大丈夫です。しかし偏差値の求め方を知ることで、偏差値は、母集団の学力レベルが高いと低くなり、低いと高くなることがお分かりになったかと思います。そこで次章では、中学受験の偏差値の特徴を母集団の観点からお話します。
中学受験の偏差値の特徴
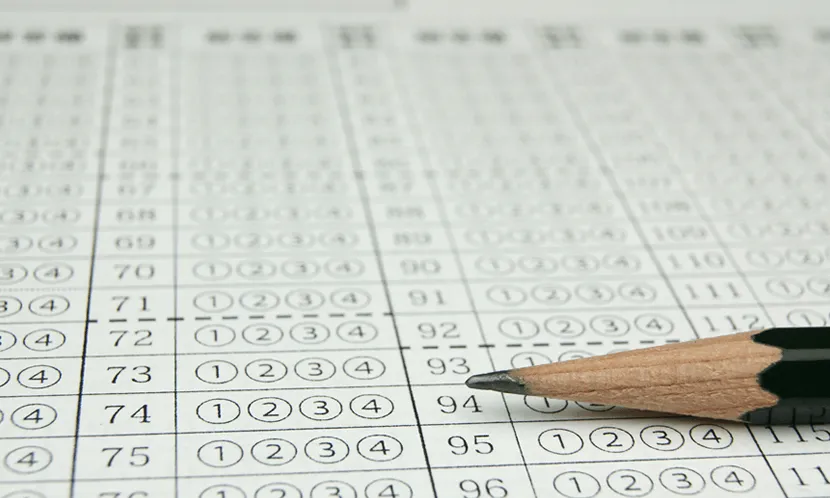
中学受験においても、学力偏差値は「相対的な学力を図る指針」、学校偏差値は「合格するためには到達しておきたい数値の指針」として使われています。ただしここで注意点があります。高校受験や大学受験と同じ感覚で、偏差値を見ないようにしてください。中学受験で用いる偏差値には特徴がありますので、判断材料として正しく使うためにはまずその特徴を理解する必要があります。ここでは、その特徴についてお話しします。
中学受験における「学校偏差値50」の位置付け
「偏差値50の学校」と聞くと、たいていの方は「平均レベルの学校」というイメージを持たれるのではないでしょうか。しかし、中学受験では母集団の学力レベルが高いため学校偏差値が低めに出るようになっており、「偏差値50」は水準が高めであると言えます。
中学受験を希望する小学生が少ない上、彼らのほとんどは塾に通い熱心に学習に取り組んでいるため、母集団は小さいですが、全体的な学力レベルが高いのが特徴です。一方高校受験に挑戦する高校生は、中学受験希望者よりずっと人数が多いため母集団が大きくなり、その中でも熱心に学習に取り組む層とマイペースな層とで分かれるので、個々の学力レベルの差が大きくなります。そのため、中学受験での「偏差値50」と、高校受験での「偏差値50」を比べると、中学受験の方がレベルは高くなります。
例えば、中部エリアの人気校である愛知中学校は、中学受験では45(名進研)/43(日能研)で設定されていますが、高校受験の模試では愛知高校・選抜クラスは15ポイント近く上がっています。これは愛知中のレベルが低くて、高校が高いのではなく、母集団の違いにより生じる現象になります。
そのため、中学受験を行う際、高校受験や大学受験のような感覚で「学校偏差値50は平均レベル」と考えるのは間違いです。実際に、偏差値50の中学校にも大学進学実績が優れているところはたくさんありますし、しっかりと受験対策を行わなければ偏差値50の私立中学校に入試で合格することはたやすいことではありません。
模試ごとに学力偏差値が異なる
中学受験の準備をしていく中で、さまざまな模試を受けることになりますが、受ける模試ごとに偏差値が大きく異なる場合があります。これは、「模試を受けている生徒たち(母集団)の学力レベル」が大きく影響しています。
例えば、SAPIX(サピックス)が主催した模試を受けたとしましょう。SAPIX小学部は、難関中学を目指す受験生が多く集まったハイレベルの中学受験学習塾ですので、その塾が主催する模試はそもそもの母集団の学力が高く、結果、低めの偏差値が出ます。
中学受験学習指導塾の大手としては、四谷大塚と日能研があげられますが、両者とも、受験者数が多くさまざまな学力レベルの受験生が模試を受けますので、SAPIXの模試に比べるとのやや高めの偏差値が出る傾向にあります。
模試の傾向としては、日能研は四谷大塚に比べやや難易度が高いとされ、難関中学の合否を推し量るのに使われます。また模試の結果が出るのも早く成績の分析資料が充実している点で、大きな支持を得ています。四谷大塚は、出題の難易度のバランスが良いと言われており、そのため受験者数は中学受験対応学習塾が開催する模試の中で一番多いのが特徴です。ちなみに名進研では、日能研の模試を採用しています。
名進研公開模試の場合は、母集団は地元の受験生が中心で、6年生の志望校判定も地元の学校が中心となっています。そのため名進研公開模試は、上位校の偏差値設定が地元の南山中女子部や東海中になるので、全国の小学生を対象とし上位校の偏差値設定が開成中や灘中になる日能研公開模試よりも、偏差値が高くなる傾向があります。
このように、偏差値は模試により異なるのですが、これは模試の性格的なもので、どちらが正しい数値というものではありません。
正確性が出るのは6年生の夏休み以降
中学受験に挑戦するために、早ければ小学校低学年、一般的には4年生・5年生から勉強を始める小学生が多数派です。しかし、偏差値が合格のボーダーラインの参考資料として使えるようになるのは、6年生の夏以降の偏差値になります。5年生の3学期以降から、中学受験に対する意識が一段と高くなって本腰を入れて勉強に取り組み始め、そして夏休みの時期に集中的に追い込んで劇的に実力を上げる生徒も多くいますから、それ以前の偏差値は、勉強習慣の定着具合や苦手科目の分析などで活用するようにしましょう。
偏差値の活用方法
同じ種類の模試で偏差値を見る
中学受験向けの模試には、SAPIX主催の「合格力判定サピックスオープン」、日能研の「全国公開模試」、四谷大塚の「合不合判定テスト」、首都圏模試センターによる「統一合判」、名進研による「名進研公開模試」など様々なものがありますが、毎回受ける模試を変えてしまうと、母集団の学力レベルも変わってしまいますので、偏差値の正しい比較ができなくなります。偏差値を正しく活用するためには、主催者が同じ模試を通年で受けるようにしましょう。この時、「全国の小学生を対象にした模試」、「中部エリアを対象にした模試」といった母集団の異なる2種類の模試を受けるようにすると、良い比較材料となり自分の相対的な学力レベルがわかります。
偏差値の推移で成績の伸びを見る
通年で同じ模試を受けると、偏差値の推移もはっきりわかるようになります。この時、数値の上がり下がりだけを見て一喜一憂するのではなく、模試のデータをしっかり確認して「良かった点」や「悪かった点」を洗い出しましょう。その上で、偏差値の下がった教科ではその原因を特定し、どうすれば次回の模試で実力を発揮できるか対策を立てるようにしてください。模試の結果を偏差値のチェックだけで終わらせるのはとてももったいないので、模試結果のデータを活用して学力アップにつなげていきましょう。
受験校の選定
受験校の選定のために、偏差値を活用することもできます。偏差値からは「合格の確率」を推し量ることができますので、より受かりやすい中学校を予測して選ぶことが可能です。
ただし、偏差値だけで学校選びをするのはおすすめしません。偏差値は、「このくらいの学力があると合格しやすい」ことを数値で表したもので、学校の教育内容、校風、授業内容とは一切関係がないのです。そのため偏差値は、学校選びの一つの要素にはなりますが、絶対的なものではありません。
偏差値が高くてあこがれていた学校に実際に見学に行ってみると、学校の雰囲気が子どもには合わないと感じたり、その逆の場合も多々あります。そのため学校選びは、まずは数多くの学校に子どもと一緒に足を運び、教育方針や校風、通学経路の状況などをチェックすることから始めましょう。その上で、「その学校に入るためにはどのくらいの学力が必要なのか」を、偏差値を参考にして学習を組み立てるのが正しい受験校の選定方法です。
偏差値を上げるための方法
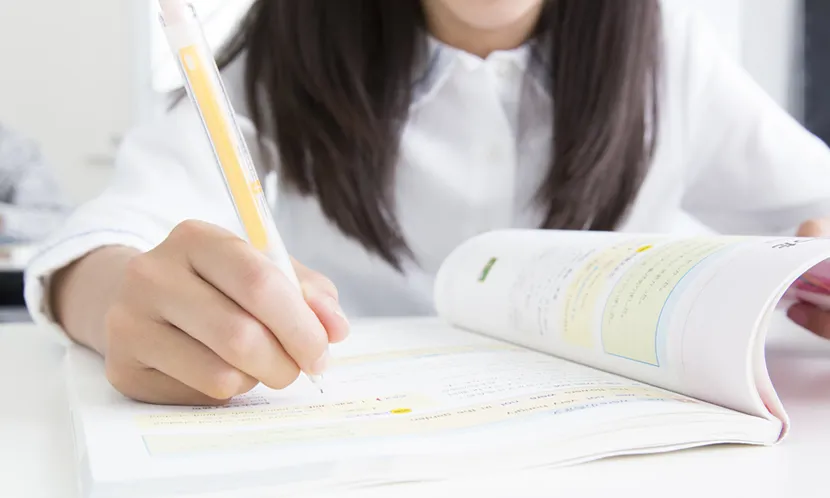
偏差値を上げるための勉強方法として効果的なものを、「普段の学習」と「模試」において2つ挙げます。参考にし、ぜひ日々の学習習慣に取り入れてください。
・普段の学習では
予習と復習を行って学力を定着させる
塾の授業前に、予習を行って学ぶ内容をざっと把握してから授業に臨むようにすると、授業内容が頭に入りやすくなります。また、授業中に分からなかった箇所はその日中に塾の先生に質問をして解決しましょう。帰ってからは、その日学んだ内容をしっかり復習し、重要なところは暗記してください。そして一度覚えたものは忘れないよう、定期的に復習して覚え直します。人間の脳は、覚えたものは時間がたつと忘れる構造になっているので、定期的に覚え直しをしないと、学習効果が期待できません。
予習⇒授業⇒復習⇒重要箇所を暗記⇒一定期間後に覚え直し
このサイクルで学習を行うようにしましょう。予習と復習のバランスは、2:8、もしくは3:7くらいで大丈夫です。
苦手分野を克服する
苦手分野があるとそこで足を引っ張ってしまい、思い通りの偏差値が出にくくなります。苦手分野ができる理由にはいくつかありますが、「その分野に触れている時間が少なく、何となく理解で済ませてしまっている」場合であることが多いです。
この場合は、土日祝で空いている1日を定期的に確保して、集中的に勉強に取り組んでください。自分で分かりそうなところは自分で調べ、分からないところはまとめて塾の先生に質問しましょう。もし、実際に授業で使っているテキストのレベルが難しいと感じる場合は、基礎が詳しく解説されている薄めの問題集を一冊解くと理解が深まります。
苦手分野は早めに対策をし、克服することが、偏差値向上への近道です。
・模試では
基礎問題を落とさない
模試では、基礎問題を確実に得点できるよう普段からトレーニングしましょう。正答率の高い基礎問題を落とすと、偏差値が思うように出なくなります。
模試を解き直す
模試が終わり模範解答をもらったら、一度模試をじっくりと解き直して解説を読みましょう。模試で出る問題は実際の受験の場でもよく問われることが多いので、模試の解き直しは実力アップに非常に効果的です。
志望校判定の見方

6年生の秋の時期になると、模試の結果の他「志望校判定」も出力されるようになります。これは、昨年の合格者における偏差値の統計を基準にして「合格する率が高い」、「あと一歩」などと分析し、合格率の判定を行ったものです。こちらの見方も注意しなくてはいけません。
実際の合否は「幅」で出る
模試では便宜上、一つの偏差値(数値)から「合格率」を編み出しますが、実際の入試での合否判定は、「ここからここまでの偏差値帯の受験生が合格する」というもので、「幅」で動いています。そのため、「各模試で志望校判定が80%以上の偏差値を出しておかないと合格できない」ということではありません。実際に模試を受けるとわかりますが、各模試では志望校判定50%、20%などの偏差値も設定されています。志望校判定が低くても、当日の試験で「合格の幅」に入れるように努力を重ねれば、合格を勝ち取れる可能性は大いにあります。
志望校判定は参考程度にとどめる
例えば10月に模試を受けて、とある受験校の志望校判定が出ても、それはあくまで10月時点での学力を基に出された判定であって、入試当日の合否を占うものではありません。仮にかんばしくない判定結果が出たとしても、模試結果は、入試までにどの教科、単元の学習に力を入れればいいかを分析して、学習を組み立てるための判断材料にすればよいのです。「判定がよくないからもう志望校をあきらめよう」と判断するのは間違った志望校判定の見方で、模試を受験する意義がなくなります。また、判定がよい結果で、それで安心してしまって勉強に手を抜いてしまうと、入試当日思わぬ結果になることもあります。判定がよい結果であればそれを維持できるように一層努力し、よくない結果であればそれをくつがえすためにさらに努力を積み重ねる、それが志望校判定の正しい見方です。
偏差値一覧(愛知、岐阜、三重県の私立中学)
受験の世界では偏差値が一つの物差しになっています。中学受験だけでなく高校・大学の受験も偏差値の存在は大きいです。
この地区で多くの中学受験生が受ける名進研と日能研の公開模試、主だった中学校の「合格率80%の偏差値」は下記のようになっています。愛知中を例にすると、名進研では総合偏差値45、日能研では43以上の結果なら、合格する可能性が高いことを下記の情報は表しています。
| 学校名 | 名進研公開模試 | 日能研公開模試 | |
|---|---|---|---|
| 共学校 | 愛知中 | 46 | 43 |
| 愛知工業大学名電中 | 40 | 37 | |
| 大成中 | 40 | 37 | |
| 滝中 | 60 | 59 | |
| 中部大学春日丘中 | 43 | 38 | |
| 鶯谷中 | 42 | 40 | |
| 高田中 | 54 | 53 | |
| 男子校 | 海陽中(入試Ⅰ) | 54 | 51 |
| 東海中 | 64 | 59 | |
| 名古屋中 | 51 | 49 | |
| 南山中男子部 | 52 | 49 | |
| 女子校 | 愛知淑徳中 | 53 | 51 |
| 金城学院中 | 41 | 42 | |
| 椙山女学園中 | 35 | 40 | |
| 南山中女子部 | 64 | 60 |
まとめ
どんなに学力の高い受験生でも、「合格率100%」ということは受験の世界ではありえません。当日、高熱や腹痛で実力が発揮できないこともあります。また、合格率20%でも、入試直前の頑張りで学力が大きく伸び、入試直前で合格率80%近い学力になって合格をつかむ受験生もいます。偏差値や志望校判定の結果だけをみて振り回されるのではなく、正しい見方で活用することが、合格への道になることを覚えておきましょう。
名進研は、中学・高校受験の専門予備校です。中学・高校受験コースでは、受験教育のエキスパートである講師陣が授業を担当し、ポイントを押さえた指導でお子さまの学力を最大限に伸ばします。なお、能力を飛躍的に向上させて上位校を目指す際は、通常の授業に合わせて能力開発コースの「速読・読解力講座」もお試しください。右脳を鍛えるトレーニングで、脳の潜在能力アップが期待できます。中学受験は、首都圏の有名中学に圧倒的な合格実績を誇る進学塾SAPIXのカリキュラムで、高校受験では、名進研が培った中部地域の難関校突破のためのノウハウを用いて指導を行い、名進研受講生全員の難関校合格を目指します。
名進研の中学受験・高校受験コース、およびその他能力開発コースを有効活用していただき、お子さまの将来の可能性を広げてください。お問い合わせ・資料請求は、メール・電話で受付中です。ご連絡お待ちしております。
こちらの記事もオススメ
| Tweet |