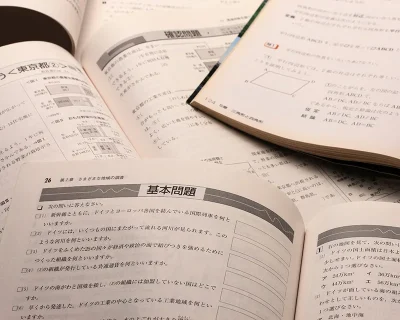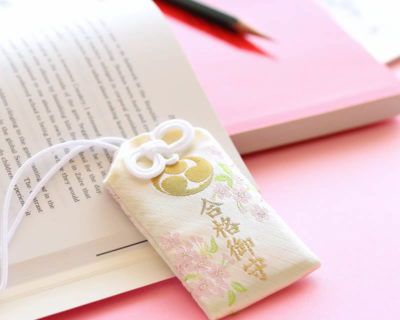集中力アップに最適!東大生も愛用する勉強中のお供お菓子と勉強法

勉強をしていると、時々小腹が空いてお菓子が食べたくなることがありますよね。
空腹を感じると、集中力が落ちて思考が鈍くなり、頭が働かなくなることもあります。
例えば、「なかなか勉強に集中できないな」とか「今日は勉強がうまくいかないかも」と感じることがあるかもしれません。
そんな時には、美味しいお菓子を食べてリフレッシュしたくなります。
勉強は複雑な問題を解決したり、何度も学んで記憶することが求められるため、ストレスがかかり、脳がエネルギーを欲しがることがあります。その結果、空腹を感じやすくなるのです。
このような状況では、勉強にプラスの効果がある頭を働かせるブドウ糖などのエネルギー源となるお菓子を食べ、勉強の効率を向上させたいものです。
糖分を脳に供給するだけでなく、努力のご褒美としてお菓子を楽しむことも、モチベーションを高める要因となります。
今回は勉強中に食べるべきオススメのお菓子を紹介します。
主に「ファミリーマート、ローソン、セブンイレブンなどのコンビニでも買える安いお菓子」「脳に直接届く栄養素が含まれたお菓子」、「勉強への集中力を高めるお菓子」、「食べても太らない、ヘルシーな身体にも優しいお菓子」「塩味があるしょっぱいお菓子」を紹介します。
この記事では、集中力を持続させるための最適な勉強のお供、特に間食やおやつに最適なお菓子の選び方から、東大生が実際に愛用しているおすすめ商品まで、具体的な例を交えて詳しく解説します。勉強中の集中力アップに効果的な栄養素、糖分やカロリー摂取の注意点、歯や胃への負担軽減など、お菓子選びで失敗しないためのポイントを網羅。チョコレートやグミなど種類別のおすすめ商品だけでなく、気分転換に最適なお菓子もご紹介します。さらに、お菓子以外に集中力を高める飲み物、音楽、アロマなども紹介。カフェインの摂取方法やノンカフェイン飲料、集中できる音楽ジャンル、アロマオイルなど、学習効率を上げるための具体的な方法が分かります。タイマーを使った時間管理術や休憩の取り方、勉強場所の選び方など、快適な学習環境を作るためのコツも合わせて解説することで、この記事を読めば、自分にぴったりの勉強のお供を見つけ、集中力を持続させ、効率的に学習を進めることができるでしょう。
勉強のお供に最適なお菓子の選び方

勉強中のお菓子選びは、集中力を持続させるための重要なポイントです。単に甘いものを食べるだけでなく、脳の働きをサポートする栄養素を含むお菓子を選ぶことが大切です。また、食べ過ぎによるデメリットにも注意が必要です。ここでは、勉強のお供に最適なお菓子の選び方について、栄養面と注意点の両面から解説します。
集中力持続に効果的な栄養素
集中力を維持するためには、脳にエネルギーを供給し続けることが重要です。ブドウ糖や脂質は脳のエネルギー源となるため、これらの栄養素を効率よく摂取できるお菓子を選ぶと良いでしょう。
ブドウ糖を素早く補給できるお菓子
ブドウ糖は脳の主要なエネルギー源です。勉強中に集中力が途切れたと感じたら、ブドウ糖を素早く補給できるお菓子が効果的です。ラムネ、グミ、チョコレートなどはブドウ糖を豊富に含んでいます。ただし、急激な血糖値の上昇は眠気を引き起こす可能性があるため、少量をこまめに摂取するようにしましょう。
| お菓子の種類 | 特徴 | 摂取量の目安 |
|---|---|---|
| ラムネ | 吸収が早く即効性がある | 3~4粒 |
| グミ | 持ち運びに便利 | 5~6個 |
| チョコレート | カカオポリフェノールも含まれる | 1~2かけ |
脳のエネルギー源となる脂質を含むお菓子
脂質も脳の重要なエネルギー源です。ナッツ類、アーモンドチョコレート、ソイジョイなどは良質な脂質を含んでいます。脂質は消化吸収に時間がかかるため、腹持ちが良いというメリットもあります。間食としてだけでなく、朝食やお弁当に取り入れるのもおすすめです。
| お菓子の種類 | 特徴 | 摂取量の目安 |
|---|---|---|
| ミックスナッツ | ビタミン、ミネラルも豊富 | 10~20g |
| アーモンドチョコレート | ブドウ糖と脂質を同時に摂取できる | 2~3粒 |
| ソイジョイ | 大豆イソフラボンも含まれる | 1/2~1本 |
勉強中の間食で注意したいポイント
勉強中にお菓子を食べる際には、集中力を阻害しないよう、いくつかの注意点に気を付けましょう。糖分やカロリーの摂りすぎ、歯や胃への負担など、お菓子の食べ過ぎによるデメリットを理解し、適切な量と頻度を心がけることが大切です。
糖分・カロリーの摂りすぎに注意
糖分の摂りすぎは、血糖値の急上昇と急降下を引き起こし、集中力の低下や眠気につながる可能性があります。また、カロリーの摂りすぎは肥満の原因にもなります。お菓子を選ぶ際には、糖質やカロリーの低いものを選ぶ、もしくは少量をこまめに摂取するように心がけましょう。また、人工甘味料の過剰摂取も健康への影響が懸念されるため、注意が必要です。
歯や胃への負担を軽減
飴やキャラメルなど、糖分の多いお菓子を長時間口に含んでいると、虫歯のリスクが高まります。勉強中のお菓子は、なるべく短時間で食べられるものを選び、食べた後は歯磨きやうがいをするようにしましょう。また、空腹時に一度に大量のお菓子を食べるのは、胃腸への負担が大きいため、避けるべきです。少量ずつ、時間を分けて食べるようにしましょう。チョコレートやグミなど、噛み応えのあるお菓子は、満腹感を得やすく食べ過ぎを防ぐ効果も期待できます。
東大生が愛用する!おすすめのお菓子10選

東大生の間で勉強のお供として人気のお菓子を10種類ご紹介します。集中力持続や気分転換に役立つお菓子を厳選しました。それぞれのメリット・デメリットも合わせて解説するので、自分に合ったお気に入りを見つけて、勉強効率をアップさせましょう!
【脳の唯一の栄養素】ブドウ糖を効率的に摂れるお菓子とは
まず、勉強中に食べるお菓子は「ブドウ糖を含むもの」を考慮することが重要です。
これは「ブドウ糖が脳にとって唯一の栄養源」であり、学習時に脳が多くのエネルギーを消費するため、適切に補給することで集中力を高めることができるからです。
ブドウ糖を効率的に摂取できるお菓子としては、ラムネやチョコレートが推奨されます。
・ラムネはブドウ糖が多く含まれている商品がでその中でも「森永ラムネ」はなんとブドウ糖が90%以上も含まれています。
森永ラムネは、東京大学の学生にも支持されていることが東京大学新聞に掲載されています。
カバンにラムネを常備しておき、軽い空腹感や脳の疲労を感じた際に摂取するのが効果的です。
リンク先 東大新聞(http://www.todaishimbun.org/ramune20181005/)
チョコレート
チョコレートは、集中力アップに効果的なカカオポリフェノールやテオブロミンを含んでいます。糖分も含まれているため、脳のエネルギー源としても最適です。
おすすめのチョコレート3選
| 商品名 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 明治ミルクチョコレート | 定番のミルクチョコレート。まろやかな甘さが特徴。 | 手軽に購入できる、価格が手頃 | カカオ含有量が少ない |
| 森永ダース | 一口サイズのチョコレート。持ち運びに便利。 | 個包装で食べやすい、勉強の休憩に最適 | 一度にたくさん食べてしまう可能性がある |
| meiji THE Chocolate | カカオの風味を活かした高カカオチョコレート。 | 集中力向上効果が高い | 苦味が強い、価格が高い |
グミ
グミは、手軽に食べられる持ち運びやすさが魅力です。噛むことで脳が刺激され、集中力アップに繋がるとも言われています。様々なフレーバーがあるので、気分に合わせて選べるのも嬉しいポイントです。
おすすめのグミ3選
| 商品名 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| HARIBO ゴールドベア | 世界中で愛される定番グミ。様々なフルーツフレーバーが楽しめる。 | 硬めの食感で噛み応えがある | 糖分が多い |
| 果汁グミ | 果汁をたっぷり使用した、ジューシーなグミ。 | 果物の栄養素を摂取できる | べたつきやすい |
| ピュレグミ | 表面がパウダーでコーティングされた、独特の食感が楽しめるグミ。 | 豊富なフレーバー展開 | 一度にたくさん食べてしまう可能性がある |
その他のお菓子
チョコレートやグミ以外にも、勉強のお供に最適なお菓子はたくさんあります。気分転換に最適なスナック菓子や、小腹を満たせるクッキーなど、好みに合わせて選んでみましょう。
おすすめのその他のお菓子4選
| 商品名 | 特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ポテトチップス うすしお味 | 定番のポテトチップス。塩味が勉強中の気分転換に最適。 | 手軽に購入できる | 脂質・塩分が多い |
| 堅あげポテト うすしお味 | 堅い食感が特徴のポテトチップス。噛み応えがあり、満腹感を得やすい。 | 食べ応えがある | 音が少し気になる場合がある |
| アルフォート | チョコレートとビスケットの組み合わせが絶妙なお菓子。 | 甘すぎず、食べやすい | 食べていると手が汚れる場合がある |
| ビスコ | クリームをサンドしたビスケット。小腹を満たすのに最適。 | 栄養価が高い | 割れやすい |
人工甘味料にも注意をしましょう
お菓子を楽しむ際に気をつけたいのが、人工甘味料です。
特にカロリーゼロやカロリーオフの製品には注意が必要です。人工甘味料はカロリーが少ないとされていますが、摂取することで精神的な不調や中毒のリスクが指摘されています。
代表的な人工甘味料には「アスパルテーム」「アセスルファムK」「スクラロース」などがあります。
ラベルをしっかり確認して、人工甘味料が含まれていない商品を選ぶようにしましょう。
ジュースを飲むときも、カロリーを気にするだけでなく、人工甘味料が入っていないものを選ぶことをおすすめします。
お菓子以外の勉強のお供
勉強のお供には、お菓子だけでなく、飲み物、音楽、香りなど、様々なものが考えられます。集中力を持続させ、学習効率を高めるためには、自分に合ったお供を見つけることが重要です。ここでは、お菓子以外のおすすめの勉強のお供と、その効果的な活用方法についてご紹介します。
飲み物
勉強中の水分補給は、集中力を維持するために不可欠です。適切な飲み物を選ぶことで、より効果的に学習を進めることができます。
カフェインの効果的な摂取方法
カフェインには、覚醒作用や集中力向上効果があります。コーヒーや緑茶などに含まれるカフェインを摂取することで、眠気を抑え、学習効率を高めることができます。ただし、過剰摂取は、不眠や不安などの症状を引き起こす可能性があるため、適量を守ることが重要です。カフェインの効果が現れるまでには30分ほどかかるため、勉強開始の少し前に摂取するのがおすすめです。また、カフェインの効果持続時間は個人差がありますが、一般的には4~6時間程度と言われています。夕方以降の摂取は、睡眠に影響を与える可能性があるため、控えるようにしましょう。
おすすめノンカフェイン飲料
カフェインを摂取したくない方や、就寝前に勉強する方には、ノンカフェイン飲料がおすすめです。麦茶、ルイボスティー、ハーブティーなど、様々な種類があります。特に、リラックス効果のあるハーブティーは、勉強中の緊張を和らげ、集中力を高めるのに役立ちます。また、ミネラルウォーターも、水分補給に最適です。
| 飲み物 | 効果 |
|---|---|
| コーヒー | 覚醒作用、集中力向上 |
| 緑茶 | 集中力向上、リラックス効果 |
| 麦茶 | 水分補給 |
| ルイボスティー | 抗酸化作用、リラックス効果 |
| ハーブティー(カモミール) | リラックス効果、安眠効果 |
| ミネラルウォーター | 水分補給 |
音楽
音楽を聴きながら勉強することで、集中力が高まる、リラックスできる、気分転換になるなどの効果が期待できます。ただし、歌詞のある音楽やアップテンポな曲は、逆に集中力を妨げる可能性があるため、注意が必要です。
集中力を高める音楽ジャンル
勉強中に適した音楽ジャンルは、クラシック音楽、アンビエントミュージック、環境音楽などです。これらの音楽は、歌詞がなく、一定のリズムで繰り返されるため、集中を妨げることがありません。また、自然の音を取り入れた音楽も、リラックス効果があり、おすすめです。
勉強用BGM配信サービス
YouTubeやSpotify、Apple Musicなど、様々な音楽配信サービスで、勉強用のBGMが配信されています。これらのサービスを利用することで、自分の好みに合った音楽を簡単に見つけることができます。また、ホワイトノイズやピンクノイズなどの環境音も、集中力を高める効果があるとされています。
| 音楽ジャンル | 効果 | 配信サービス例 |
|---|---|---|
| クラシック音楽 | 集中力向上、リラックス効果 | YouTube, Spotify, Apple Music |
| アンビエントミュージック | リラックス効果、集中力向上 | YouTube, Spotify, Apple Music |
| 環境音楽 | リラックス効果、集中力向上 | YouTube, Spotify, Apple Music |
| ホワイトノイズ | 集中力向上、ノイズキャンセリング | YouTube, Spotify, Apple Music |
| ピンクノイズ | リラックス効果、集中力向上 | YouTube, Spotify, Apple Music |
アロマ・香り
香りも、勉強のお供として有効です。特定の香りは、集中力や記憶力を高める効果があるとされています。アロマオイルやディフューザーなどを活用して、快適な学習環境を作りましょう。
集中力アップに効果的な香り
集中力を高める効果があるとされる香りには、ローズマリー、ペパーミント、レモンなどがあります。これらの香りは、脳を活性化させ、集中力や記憶力を向上させる効果が期待できます。また、ラベンダーやカモミールの香りは、リラックス効果があり、勉強中のストレスを軽減するのに役立ちます。
おすすめのアロマオイル
アロマオイルを使用する際は、ディフューザーやアロマストーンなどを用いるのが一般的です。無印良品や生活の木など、様々なメーカーからアロマオイルが販売されています。自分の好みに合った香りを選び、適量を使用するようにしましょう。また、柑橘系の精油は、光毒性があるため、使用後に直射日光を浴びることは避けましょう。
| 香り | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| ローズマリー | 集中力向上、記憶力向上 | アロマオイル専門店、無印良品、生活の木 |
| ペパーミント | 集中力向上、リフレッシュ効果 | アロマオイル専門店、無印良品、生活の木 |
| レモン | 集中力向上、リフレッシュ効果 | アロマオイル専門店、無印良品、生活の木 |
| ラベンダー | リラックス効果、安眠効果 | アロマオイル専門店、無印良品、生活の木 |
| カモミール | リラックス効果、安眠効果 | アロマオイル専門店、無印良品、生活の木 |
自分に合った勉強のお供を見つけることで、学習効率をアップし、快適な学習環境を作りましょう。
勉強のお供で集中力アップ!快適な学習環境を作るコツ
勉強のお供にお菓子や飲み物、音楽などを用意するだけでなく、学習環境を整えることも集中力アップに繋がります。ここでは、タイマーを使った時間管理術、休憩の取り方、勉強場所の選び方など、快適な学習環境を作るためのコツを紹介します。
タイマーを使った時間管理術
タイマーを使って勉強時間を区切ると、集中力を維持しやすくなります。ポモドーロテクニックのように、25分勉強して5分休憩するサイクルを繰り返す方法がおすすめです。タイマーを使うことで、時間を意識しながら勉強に取り組むことができ、ダラダラと勉強してしまうのを防ぎます。また、休憩時間を設けることで、集中力を回復させ、より効率的に学習を進めることができます。
おすすめのタイマーアプリ
- Studyplusタイマー
- Focus To-Do
- Forest
休憩の取り方
休憩時間には、軽い運動やストレッチ、瞑想などを行うのがおすすめです。長時間同じ姿勢でいると、体がかたまってしまい、集中力が低下する原因となります。5分程度の短い休憩時間でも、体を動かすことでリフレッシュできます。また、軽いストレッチは、肩こりや腰痛の予防にも効果的です。目を休ませるために、遠くの景色を見るのも良いでしょう。
効果的な休憩方法
| 方法 | 効果 | 時間 |
|---|---|---|
| 軽い運動(散歩、ストレッチなど) | 血行促進、気分転換 | 5~10分 |
| 瞑想、深呼吸 | リラックス効果、集中力向上 | 5~10分 |
| 仮眠 | 疲労回復 | 15~20分 |
| 読書(勉強とは関係のないもの) | 気分転換、知識の吸収 | 10~15分 |
勉強場所の選び方
勉強場所は、集中できる静かな環境を選ぶことが大切です。図書館や自習室など、勉強に適した場所を利用するのも良いでしょう。自宅で勉強する場合は、自分の部屋やリビングなど、集中できる場所を選びましょう。周りの音が気になる場合は、ノイズキャンセリングイヤホンや耳栓を使うのも効果的です。また、机の上は整理整頓し、必要なものだけを置くようにしましょう。散らかった机の上は、集中力を妨げる原因となります。
勉強場所を選ぶ際のポイント
- 静かで集中できる環境
- 適切な照明
- 快適な温度・湿度
- 整理整頓された机
- インターネット環境(オンライン学習の場合)
自分に合った勉強場所を見つけることで、学習効率を大幅に向上させることができます。周りの環境に左右されずに、集中して勉強に取り組めるように、最適な学習環境を作り上げましょう。
まとめ
勉強のお供は、集中力を持続させ、学習効率を上げる上で重要な役割を果たします。この記事では、東大生が愛用するお菓子を中心に、集中力アップに効果的なお供の選び方や、お菓子以外の飲み物、音楽、香りなどの活用法を紹介しました。
お菓子を選ぶ際には、ブドウ糖や脂質といった脳のエネルギー源となる栄養素を含むものを選び、糖分やカロリーの摂りすぎに注意することが大切です。チョコレートに含まれるカカオポリフェノールは集中力向上に効果があり、グミは手軽に食べられる持ち運びやすさがメリットです。その他、気分転換にスナック菓子を取り入れるのも良いでしょう。森永製菓のダースや、明治のチョコレート効果、果汁グミなどはおすすめです。
お菓子以外にも、カフェインを適度に摂取したり、リラックス効果のあるノンカフェイン飲料を飲んだりすることも効果的です。また、集中力を高める音楽やアロマを活用することで、より快適な学習環境を作ることができます。作業用BGM配信サービスのStudyplusなどを利用するのも良いでしょう。
さらに、タイマーを使った時間管理や適切な休憩、集中できる勉強場所の確保も重要です。自分に合った勉強のお供を見つけ、快適な学習環境を整えることで、学習効果を最大限に高めましょう。
こちらの記事もオススメ
| Tweet |