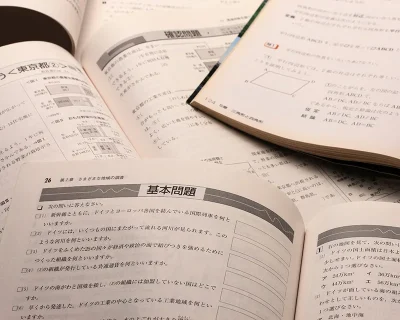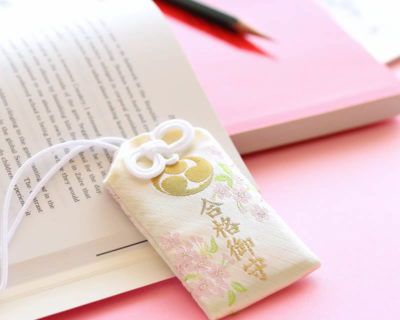高校受験は内申点で決まる?評定平均の計算方法と点数アップ対策
シリーズ私立中講座

高校受験に影響する「評定」とは?その算出方法は?
- 目次
評定とは何か
評定とは、中学校において一般的に「内申点」と呼ばれるものを指します。内申点とは在学中3年間に学習した各教科の成績をまとめた指標で、その内容が記録された公式の判定資料を「内申書」といいます。評定の対象となるのは、国語・数学・理科・社会・英語の5教科に加え、保健体育・技術・家庭科・美術・音楽といった実技4教科を含めた合計9教科です。これらすべての教科は統一して5段階で評価される仕組みとなっており、どの分野もバランス良く学習していくことが求められます。
内申書には「各教科の学習の記録」として、科目ごとの評定が詳細に記載されます。つまり、中学校で履修するすべての教科が評定の対象であるため、定期テストなどで各教科をまんべんなく得点できることが大きな強みになります。さらに東京や神奈川県では、5段階の評定に加えて「観点別評価」と呼ばれる評価項目も設けられています。これは「関心・意欲・態度」「知識・理解」「思考・判断」「技能・表現」という複数の視点から、教科ごとの学習の到達度を測定する仕組みです。観点別評価はA・B・Cの3段階で表され、学力だけでなく学習姿勢や表現力などの側面も可視化されるのが特徴です。
また、どの学年の評定が内申書に記載されるかは都道府県によって違いがあります。例えば東京都や愛知県の場合は中学3年時の評定のみが対象になりますが、神奈川県では中学2・3年の2年間の評定が、埼玉県では在学3年間すべての評定が記載されるといったように、地域ごとに扱いが変わります。そのため、自分が受験する地域の取り扱いをあらかじめ理解しておくことが非常に大切です。
さらに、内申書には評定だけでなくその他の重要な情報も盛り込まれます。内容は都道府県や学校によって若干異なりますが、一般的には部活動や校内での行動の記録、授業を受けた期間や欠席日数といった出欠状況、そして教師による総合所見(総合的な評価欄)などが記載されます。つまり内申書は、学習成績だけでなく学校生活全体を反映する資料としての役割を果たしているのです。
校内活動や部活動が評定(内申)に影響する可能性

前述したように、内申書には評定だけでなく、生徒が学校内で取り組んできた活動の記録が含まれることがあります。ここで言う活動とは、生徒会や委員会といった校内での役割、さらには部活動での実績などです。地域によっては校外での活動、たとえば地域ボランティアや社会貢献活動の記録までが評価の対象として扱われることもあります。具体的には千葉県や埼玉県では、校内活動や部活動に加え、校外活動も入試の合否を判断する材料として位置づけられています。ただし、こうした活動の評価はあくまでも補助的なものであり、学力そのものを示す定期テストの成績や内申点、出欠状況などに比べれば配点の比重は小さく、直接的な影響は限定的です。それでも「学習以外の分野でも努力している姿勢」を伝える材料になるため、学校生活に積極的に取り組むことは決して無駄にはなりません。
評定平均の出し方
評定平均の算出方法は基本的にシンプルです。9教科の評定をすべて合計し、その合計値を教科数(この場合は9)で割ると評定平均となります。例えば、国語・数学・社会・英語の評定がそれぞれ4、理科が3、さらに保健体育・美術・技術家庭科がいずれも5であった場合、合計点は39になります。この合計を9教科で割ると「4.3」という数値が得られます。なお、算出の際は小数点第2位で四捨五入されるため、3.55は3.6に、4.65は4.7というように整理される仕組みです。こうした処理により、評定平均は見やすく、統一的な数値として活用されます。
ここで示した例は東京都のように中学3年次のみを対象とした場合の算出方法です。しかし、実際には都道府県ごとに評定平均の扱い方や計算方式には細かな違いがあります。例えば愛知県の場合は、9教科の評定合計を単純に2倍したものを「内申点」として採用します。また、受験する学科の特性に応じて一部の教科の評定を加重して扱う「傾斜配点」が導入されるケースもあります。たとえば音楽科を志望する生徒は音楽の評定が倍に、美術科であれば美術の評定が倍に計算されるといった具合です。そのため、特定の専門学科を目指す場合は主要5教科だけでなく、関連する実技教科の評価にも十分注意を払う必要があります。
地域によっては実技4教科の比重が高い
国語や数学など主要5教科に集中しがちですが、実技4教科を軽視するのは危険です。東京都では実技4教科の評定を2倍にする傾斜配点が導入されているように、自治体によっては実技科目の評価を重視しているところがあります。そのため、高校受験を見据えるなら5教科だけに偏らず、保健体育・技術家庭科・美術・音楽といった実技系の教科にも全力で取り組むことが欠かせません。実技教科は単なるスキルや成果物の出来映えだけでなく、「授業にどれだけ積極的に関わっているか」という姿勢も評価の大きなポイントとなります。つまり努力する姿勢を見せること自体が、評定を高めるうえで重要な要素となるのです。
評定平均を上げるためにできること

評定の平均値を上げるためには、基礎的な学力の底上げを行うこと、課題の提出を徹底すること、そして授業態度や学習態度を改善することが重要です。これらを継続的に意識して取り組むことで、成績全体の印象が良くなり、評定アップにつながります。
定期テストの点数を上げる
もっとも直接的な方法は、定期テストで高得点を取ることです。中間テストや期末テストに向けて計画的に学習を進め、遅くとも試験の1~2週間前からは本格的に勉強を始めましょう。直前に短期間で詰め込む勉強では十分な成果を上げにくいため、早めに準備を始めるのが大切です。
試験の2週間前までは、前回のテスト範囲の続きを中心にコツコツ復習するのがおすすめです。範囲は「前回の続きから」と考えれば予想できますし、この時点で提出課題を終わらせておけば、試験直前の勉強に集中できます。1週間前からは「追い込みの時期」となりますので、課題に追われてしまうと本来の試験勉強が十分にできなくなる危険があります。
また評定は9教科すべてが対象であるため、主要5教科だけでなく実技4教科も含めて、できるだけバランスよく得点を確保することが大切です。普段から予習・復習を心がけ、理解が不十分な部分は友人や先生に質問して解決しておきましょう。
さらに効果的なのは、あえて苦手教科から優先して取り組む方法です。不得意な科目は理解に時間がかかるため、早めに着手することで余裕を持って対策ができます。直前になって焦らないように、日程を前倒しして取り組むのがポイントです。具体的には、学校のワークや問題集を繰り返し解くのが有効です。解ける問題を増やしていけば、自信がつき、自然とテストの得点にも結びつきます。
授業態度・学習態度の見直し
普段の授業態度や学習態度も評定に直結します。「授業中に積極的に発言や質問をする」「黒板や先生の話にしっかりと注意を向ける」といった基本的な姿勢を意識しましょう。特に実技教科(美術・体育・音楽など)は、得点そのものよりも授業中の取り組み姿勢が大きく評価される傾向があります。苦手意識があっても「真剣に努力している姿勢」を見せることが大切で、そうした態度が最終的な評定にプラスに働きます。
課題の提出
ノートやレポート、問題集、ディスカッション授業で配られるプリントなど、日々の課題は必ず期限を守って提出しましょう。試験の結果が良くても、課題を出していない、あるいは提出が遅れると評価は下がってしまいます。
評価対象になりやすい課題には、問題集や授業ノート、レポート、作品提出(美術の場合)、授業中のプリントやグループ学習の発表ノートなどがあります。さらに実技科目では、歌唱や楽器演奏、運動といった実技テストも加わります。つまり、定期テスト対策に集中するだけでなく、日常の課題提出や授業中の取り組みも怠らないことが、評定平均を上げるためには欠かせないのです。
評定が下がる原因

評定が下がってしまう主な要因としては、定期テストの得点が振るわないこと、授業中の態度に問題があること、そして提出物や課題をきちんとこなしていないことが挙げられます。これらはいずれも教師からの評価に直結するため注意が必要です。一度にすべてを改善するのは難しいかもしれませんが、まずは取り組みやすい部分から順に修正していくことで、徐々に弱点を補強していくことができます。小さな改善の積み重ねが、最終的には大きな評定の差につながるのです。
定期テストの点数が振るわない
最も大きな影響を及ぼすのはやはり定期テストです。点数が低ければ、どんなに授業態度が良くても評定は下がってしまいます。まずは自分が苦手としている教科や単元を明確に把握し、弱点克服を意識した学習を行いましょう。苦手範囲をあいまいにしたまま試験に臨むと改善は見込めません。自分に合った勉強法を見つけ、繰り返し練習することが重要です。
提出物・課題をきちんとこなしていない
課題の提出が遅れたり、提出自体を忘れてしまったりするのは評定を下げる大きな要因になります。特に期限を守れないという点は、理由の有無にかかわらず教師に良い印象を与えません。さらに、ただ提出すれば良いというわけでもなく、課題の完成度も評価対象です。問題集であれば一つひとつの設問をしっかり解き、授業ノートであれば色ペンや付箋を使って重要事項を整理するといった工夫が効果的です。こうした丁寧さは「真剣に学習に取り組んでいる」「自分なりに理解を深めようとしている」という印象につながり、評定のプラス要因になります。
授業態度が良くない
授業中に居眠りをしたり、机に突っ伏したまま聞いていたりといった態度はマイナス評価につながります。背筋を伸ばし、黒板や先生の方をしっかりと見て授業を受けることが基本です。さらに、授業の合間に相槌を打ったり、内容にうなずいたりすることで「きちんと聞いている」という好印象を与えることができます。加えて、ノートやメモを取る習慣を持つと効果的です。重要だと感じたことや疑問に思った点を書き残すことで、復習時に授業内容を思い出しやすくなり、定期テストの出題範囲を予想する際にも役立ちます。こうした小さな積み重ねが、自然と学習態度全体の評価を高めてくれるのです。
定期テスト対策はどう立てる?
評定の平均値を上げるためには、何よりも定期テストで得点を伸ばすことが効果的です。授業態度や課題提出ももちろん大切ですが、点数という形で明確に示される定期テストの結果は、最も直接的に評定へ影響します。ここでは、基礎学力をしっかりと固め、定期テストで成果を出すための具体的なポイントを紹介します。
教科ごとの性質を知る
各教科にはそれぞれ特有の性質があり、それに合った学習方法を取ることが成績アップの近道です。大きく分けると「暗記が中心の教科」「理解・読解力を必要とする教科」「暗記と理解の両方が求められる教科」に分類できます。
例えば国語・数学・英語は「暗記+理解型」の科目といえます。読解力や表現力に加えて、用語や文法、公式の暗記が欠かせません。特に数学は、公式を覚えるだけでなく、実際に問題を解いて定着させる演習が必要です。こうした性質を理解したうえで、自分に合った学習法を選択することが重要です。
一方で理科や社会は「暗記中心型」の科目です。単語カードを活用して基本用語を効率よく覚えることが基本となりますが、ただ用語を丸暗記するだけでは不十分です。文章問題を繰り返し解き、関連する知識をつなげて理解することで、応用問題にも対応できる力がつきます。
暗記系教科の勉強は「効率」が命
暗記科目に苦手意識を持つ人は、「とにかく丸暗記しよう」「すべてを覚えよう」としてしまいがちです。しかし、この方法では効率が悪く、記憶が定着しにくいのが現実です。暗記系教科を攻略するには、優先順位をつけて効率的に覚えることが求められます。
例えば歴史を学ぶ場合、まずは時代ごとの流れや政治の要点をまとめた文章を把握するのが効果的です。大枠を理解したうえで年号や細かい用語を覚えると、記憶が整理されやすく、テストでも応用が利きやすくなります。
また教科書や参考書の説明が分かりにくいときは、先生に質問して平易な言葉に置き換えてもらいましょう。自分の言葉で説明できるようになると、暗記は一層スムーズになります。さらに、文章を読んだ後に「つまりどういうことか」「要するに何を言いたいのか」と自問する習慣をつければ、要約力が鍛えられます。この力は暗記だけでなく、文章題や記述問題にも役立ちます。
数学の勉強では演習が大切
数学は、公式を理解して使いこなす力が評価される科目です。公式や方程式を暗記することは必要条件ですが、それだけでは不十分です。実際に多くの問題を解くことで、公式の意味や活用方法を理解できるようになります。
特に解けなかった問題は、教科書や先生の解説を参考にしながら再挑戦することが大切です。「なぜ解けなかったのか」「どこで間違えたのか」を突き止めて修正することで、理解度が深まり同じミスを防げます。この演習の繰り返しこそが数学力を着実に伸ばし、定期テストで得点を安定させる秘訣です。
英語は音読+文法の理解が大切
英語の学習では、単語や文章をノートに書き写すだけでは限界があります。音読を取り入れることで記憶が定着しやすくなり、文章のリズムや語順も体で覚えられるようになります。発音を意識することでリスニング力も向上し、試験だけでなく将来の英語運用能力にもつながります。
さらに、文法の理解も不可欠です。単語順や品詞、時制の使い方などを体系的に理解することで、正しい英文を組み立てられるようになります。例えば「時制」とは動詞の形を変えることで過去・現在・未来を表す仕組みですが、これを丸暗記するのではなく、例文を繰り返し読む・書くことで自然に身につけるのが理想的です。
音読と文法理解を組み合わせることで、英語の得点力は飛躍的に高まります。書く力・読む力に加えて聞く力も養われるため、バランス良く力を伸ばせるのです。
専門的な指導を取り入れる
定期テストの得点を上げることは、そのまま評定平均を引き上げ、高校受験での合格可能性を高めることにつながります。しかし独学での対策には限界があり、特に高校受験を見据えた学習には専門的な指導が有効です。
例えば、愛知県名古屋市に本社を置く「THE進学塾 名進研」では、小学4年生から中学3年生までを対象にした高校受験コースを展開しています。名古屋市を中心に、三重県や岐阜県など東海地域の難関校合格を目指した指導を行っており、科学的調査をもとに子供一人ひとりの適性や能力を把握。そのうえで画一的な方法にとらわれず、それぞれに合った学習法を提供しています。
こうした指導は単なる学力向上にとどまらず、自信や思考力、表現力の育成にもつながります。詳細な講座概要や合格メソッドについては、高校受験コースをご覧ください。名古屋市をはじめ東海エリアで学習塾を探している方は、THE進学塾 名進研 お問い合わせから相談できます。
こちらの記事もオススメ
| Tweet |